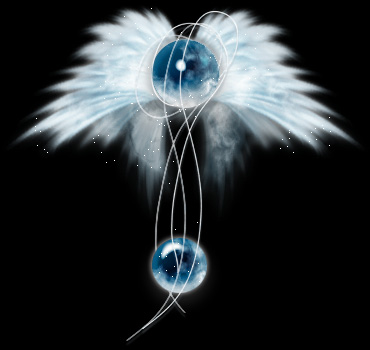
 ぺた ぺた |
| <<TOP <<BACK NEXT>> | ||
| 第34話 引 力 | ||
| ミネルバの言っていた通りに、熱の下がったリリは昼過ぎに帰宅できた。 そして翌水曜日にはいつも通りに出勤して来たと、ミネルバは ジョーに教えてくれた。今回の事は知らないことになっているジョーの元へは、特にリリから連絡はないので、ジョーがミネルバに訊いていたのだ。 何か口実を作って顔を見に行けないものかと本気で考えたジョーだったが、ショックを受けてまだ日が浅いので、焦らずに見守ろうと専門家のミネルバに言われ、おとなしく従い耐えていた。 そして今日、木曜日。ミネルバの方から連絡が来た。まずは今日のリリの様子。何事もなく出勤しているが、やはり笑顔が少ないそうだ。でも、一生懸命に空元気の笑顔を作っているらしい。ジョーはやきもきした。 「それとね、今日は私、研修があってね、診療も14時で閉めちゃうの」 「え、じゃ、あいつは?」 「もちろん上がりよ。でも、ごめんなさい、もっと早くこの事あなたに教えればよかったわね。たった今、先約が入っちゃった。ディミーから電話があってね、久しぶりに会う事になったって」 「ディミー?」 リリと会えるかもしれない幸運はあっさりとディミーにさらわれてしまった。だが、それもいいかもしれない…と健気にジョーは思い直した。女同士、楽しい時間を過ごして気分転換にでもなれば…と。 (まあ、オレは夜になれば、電話して声が聞けるしな) 今週末の家政婦業の日にちを決める口実がジョーにはあった。 (ディミーと会うんじゃ、帰りはちょっと遅くなるよな…) ジョーは腕の時計を見た。まだ昼前、11時だ。 (あと十時間ぐらい我慢すれば……) いつも電話している時間だ。その時、ディミーとまだいれば、用件だけしか言えなくなる。それでも直接声が聞ける。……あと十時間…。 たった十時間、されど十時間だ。ジョーの気分は無論後者。がっくりとうなだれた。 とぼとぼとカスタマイズ中のバイクの傍へ戻ると、深いため息が漏れた。 「なんだよジョー、朝からため息ばっかだな」 メッカに言われた。 「え、そっか?」 「な、セレ区のギャルモンとかって店に可愛いお姉ちゃんがいるんだってよ。行ってみないか、今夜」 メッカとニックは、優しい友情で、勘違いしていたのだ。ここのところずっと、まったく早く上がらなくなってしまったジョーの事を心配していた。あんなに気に入って足しげく通っていた店で、きっと何かトラブルがあったに違いない、と。 彼らの勘違いに気付いたジョーは、その温かさに思わず弱気になった。そして、一人では二進も三進も進まない難問を、ついうっかりと口にしてしまった。 「なぁ、女ってさ、どうやって口説きゃいいの?」 「え…?」 メッカとニックが振り向いた。 「だからさ、コイツを自分の女にしたいって思ったら、どうすればうまく行く?」 ニックは持っていたスパナを落とした。メッカは一瞬ぽかんとしたが、すぐに破顔して、 「おいおいおいおい、何の冗談だよ、そんなの俺らが教えて欲しいぜ! なあ?」 と、ニックに振る。スパナを拾いながら不思議そうにニックは言った。 「あ、ああ。つか、ジョーの場合、口説く必要ねーじゃん。寄って来るんだからさ」 そこでジョーは我に返った。 「ち、違う、オレじゃないぜ、ちょっとした知り合いの話だって」 慌てて言い訳するが、しかしメッカもニックも知っていた。「知り合いの話なんだけど…」の相談事は、9割が本人の悩みである、と。 二人は初めての展開に固唾をのんで、ジョーの言い分を待った。 「そいつさ、告ったコトねーし……、告ったとしても、その後どうしたらいいのか分んねぇんだってさ」 他人の話をしているはずのジョーは真っ赤である。メッカとニックは確信した。ジョーに本命が現れたのだ!あのジョーに! 宇宙一モテオの、女なんて好き放題の、とっかえひっかえ可能の、一年365人と遊べるジョーの、本命が現れたのだ!!! 「相手の女は……店のお姉さん…?」 あの気に入っていた店の女に違いないとニックは思った。本気で好きになっちまって、どうしていいかわからずに顔を出せなくなったとか? しかしすぐにジョーは否定した。 「いや、店の姉ちゃんとかじゃなくて……」 「え、そうなの?」 同じことを考えていたメッカはストレートに訊ねた。 「何してる子?」 「あー、なんか知り合いの病院で…、手伝ってるって言ってた…」 「ふーん、病院ね」 と言ってから、メッカはおや?と気づいた。 ジョーの周りで、最近、病院勤めを始めた女がいるじゃないか、と。もちろん、ニックも気づいた。でもまさか……。ジョーの周りにいるタイプとは真逆だ。 「……ぶっちゃけさ、どんな感じなわけ? その、知り合い、と彼女さん、は」 うっかり“ジョー”と言いそうになるのを、慎重に変換しながらニックが誘導する。 「そうそう、休みの日とかさ、会ってるのか?」 メッカも逸る気持ちを抑えてさりげなく訊く。 「休みは同じだから、まあ、週末は一緒に過ごしてる、らしいんだけど」 まさかそこまで進んでいるとは…と驚いたが、真っ赤なジョーが可愛くて、思わず肩をばん!と叩いて、嬉しそうにメッカが言った。 「何だよ、誘えてるんじゃねぇかよ!」 「いや、誘ってるわけじゃなくて、理由があんだってよ。相手の女ってのが、……付き合ってた男と別れて、行くトコが無くなって……、」 必死に他人事として話すジョーだが、聞いているメッカとニックの頭の中では、先ほど打ち消したばかりの女が急浮上した。経緯が似ている……というか、同じだ! 「しばらく置いてやったんだって」 「え!」 二人は驚いた。 ジョーが他人を部屋へ上げたって? 俺たちだって上がった事無いのに! 「で、そん時の借りを、今、返しに通ってるってわけでさ……」 「借りを…どんなふうに…?」 純粋に訊くニックに続いて、メッカは思わず赤裸々な想像をして、 「まさか、か、か……」 「そう、家政婦やらしてさ」 「カセイフ?」 メッカの頭の中で、躰で返させているのではなく、更にカセイフが家政婦に結びつくのにしばらくかかった。メッカのフリーズなど気付かないジョーは、だんだん焦りが募って来て、 「なあ、一緒に居るってコトは、嫌いじゃねえよな?」 と泣き言じみた事を口にし出した。ニックが、うんうんと力強く頷く。 「でも……嫌いじゃねえけど、特別好きでもねぇ…ってのも、……あるよな…?」 そうなのだ。月曜日の夜、覚悟を決めてからこの丸二日と半日、ずっとジョーなりに考えていたのだ。そして、ここまで来るとどうしていいか判らずに、いつもストップしてしまっていた。 「それは…まあ、ありかな……」 ニックが遠慮がちに言う。ああ、やっぱりか…と、失望したジョーは項垂れて、 「あー、わっかんねぇ……」 とため息をついた。他人事を装うのも忘れている。メッカが静かに言った。 「訊くしかねえよ、ジョー。今の関係じゃ不満なら、行動するしかねえって」 「行動…?」 ジョーは顔を上げた。ジョーをしっかりと見ながら、メッカはさらに励ますように、 「そうだよ、告って、返事を貰うんだよ!」 その力強さに、思わずジョーはたじろいだ。 「………メッカ、したことある?」 「数え切れねぇほどな!」 そう言って、メッカはニッと笑った。眩しい。 「そうだよ、彼女にしたいならしたいって言わないと」 「え、ニックもあるの? ディミーに?」 ジョーは驚いた。しかし、今度はニックが慌てた。 「違っげーよ、何でディミーに俺が告んなきゃなんねーの! ただ、ジョーが言ってくんなきゃ、相手の女だって分んねーだろって事だよ!」 「あ、ああ、そうか、なるほどな。いや、おまえ、今間違えたぞ、オレじゃねーって、知り合いだって」 「ああ、そか、うん、ごめん、間違えた、知り合いな」 二人でバクバクと剥がれた装いを掛け合う。ニヤニヤしていたメッカが、 「案外、相手も同じこと思ってっかもだぜ。『私のコトどう思ってるのかしら? 私は好きなのに、告ってくれないのかしら?』」 ジョーは思わずメッカを見た。期待に輝く表情で。しかし、頭の中でシュミレーションをしたのだろうか、目を伏せると弱々しく訊いた。 「………告って…、断られたら……?」 一瞬の間。しかしそこは経験豊富な年長者のメッカが答えた。 「きっぱり諦める」 ジョーはメッカを見つめたまま固まった。 ……諦める? リリを? オレが諦めるという事は、自分で独占できないどころか、他の男のモノにいつかはなってしまうという事だぞ。 ジョーは想像しただけで床にめり込みそうな気分になった。 「それか、しぶとく思い続けて、隙あらばリベンジする。長期戦で根性がいるが、でも可能性はゼロじゃない」 ああ、確かに……! と思ったが、決して嬉しい作戦ではない。 すっかり意気消沈してしまったジョーに、ニックが言った。 「毎週末、一緒にいるんだからさ、俺はイケると思うぜ。イヤイヤって感じじゃねーんだろ? 嬉しそうっつーか、楽しそうっつーか、そんな風に見えない?」 思い浮かぶリリはいつも笑顔だ。嬉しそうに見える。楽しそうに見える。 「……まあ、…そう見えるっちゃぁ、見える…かな」 カモフラージュが剥がれてもジョーは気付かないし、二人ももう突っ込まない。メッカはジョーの肩に手を置いて誘った。 「やっぱ今日は早目に仕舞って呑みに行こうぜ。さっき言ったお姉ちゃんのいる店は止めといて、女に気を遣わない店で、好きなだけ呑もう、な!」 その時、ショップへのドアが開いて、ケンが顔を出した。 「ジョー、問い合わせの電話だ」 「お、おう」 ジョーは、そそくさとケンの横を通りぬけて、ショップの中へ消えて行った。 その後ろ姿を見送って、今迄押し殺していた大発見を確かめるために、メッカとニックは顔を見合わせた。メッカがまず、口火を切る。 「なあ、相手の女ってさ……」 悩める知り合いとは、どこぞの誰かなどではなくジョー本人である事は周知のこととして、二人は口を揃えて女の名前を口にした。 「リリ?」 「ビンゴ」 ドアを後ろ手に閉めて立っていたケンがにやりと笑って言った。 「やっぱり!!!?」 二人は俄然色めき立った。 「つか、ケン、おまえ知ってたのかよ!」 メッカに言われてケンは二人の中へ飛び込んで、肩に手を掛け円陣を組み、 「こないだ病院でさ、もう、こっちが照れるほどのじゃれっぷりでさぁ!」 「マジかーーー!!!」 大興奮の二人。 「そ! ジョーなんてさ、好きだから、からかって苛めちゃうパターンでさ」 「うわ、ガキか!」 メッカは嬉しくて笑いが止まらない。 「でもリリも負けてなくてさ、ジョーの方がタジタジなんてしょっちゅうでさ」 「え! ジョーがタジタジ???」 ニックは驚いた。メッカは先を急ぐ。 「リリもジョーのこと、好きなのかよ?」 ケンは正直に話した。 「いや、そこはまだ未確認なんだけど、でも、ミネルバにも、そっと見守ってやっててくれって言われたんだ」 「ミネルバも認めてるのか! ならもう決まりじゃねーか!」 メッカの言葉に、ふとニックが気付いた事を投げかける。 「……リリ、つか、アルテミスのこと、アレンは吹っ切ってたから、問題ないんだよな、くっついたって……」 すぐさまメッカが不敵な笑いを浮かべて答えた。 「ふふふ、男と女の色恋沙汰に、良いも悪いもないぜ、ニック。あるのは唯一つ、本能に忠実な欲望だけよ!!!」 「ケダモノかよ!」 「いやでも、今回のジョーはケダモノじゃねーぜ。すっげぇ耐えてる。なんつーの、こう、触れたいんだけど、理由がないと無理、みたいな。んで、触れたら触れたで赤くなっちまったりしてさ」 「マジかよ!!」 とてもじゃないが、ジョーのそんな純情ぶりが想像できずに二人は唸った。 「本気なんだよ、ジョーは本気で絶対に欲しいんだよ、リリが…。リリの心ごとさ」 目撃者であるケンの言葉には、妙に説得力があった。 今までジョーの周りにいた、艶めかしくてグラマラスでギラギラした女とは、まるでカテゴリ違いのリリをジョーが欲しがっているというのは、なんだか不思議な気もするが、でも確かにリリはいい子だ。そこそこ可愛いし、優しいし、いつも笑顔で明るいし、アレンとの事だってきちんとさせていたし、今は自立もしている。ジョーに受けた恩はきっちり返しているようだし。 ―――ありかもしれない、ジョーとリリ。 メッカとニックは、しみじみと納得したのだった。 廊下を歩いていると、トニエントが声を掛けて来た。 「リリさん、帰り?」 「はい、お先に失礼します」 言葉少なに通り過ぎようとしたが、するりと隣に滑り込んで来たトニエントは、そのままリリの横を歩き続けた。 「そうか、エオバルト先生、今日お勉強会だもんね」 「……はい」 「それでリリさんは、これからどこかに遊びに行くの? それとも寮に帰るの?」 「友人と会います」 「友人〜? 本当かなぁ、彼氏じゃなくて?」 にやにやと笑いながら訊かれて、リリは気分が悪くなった。そもそもトニエントは苦手だったが、先日の一件以来、ますます避けたい人になってしまった。だが、あまり露骨に不快感を出すわけにもいかず、健気に大人の対応をしているリリだった。 「先生はどちらへ?」 「僕もお勉強会。エオバルト先生とは違う場所でね」 院外という事か。このままディミーとの待ち合わせの正門まで一緒なのかとげんなりした。そして、どうかディミーがもう居てくれますようにと願った。トニエントは訊きもしないのに、自分の事をベラベラと話して来る。リリは無視したい気持ちを堪えて、はあ、そうですか、と相槌だけは打ちながら、しかし彼を一度も見ずに歩いた。 病院の正門を抜けたところで、ちょうど到着したディミーとばったり会えた。ほっとしたリリに初めて笑顔が浮かんだ。手を振りながらお互いに小走りに駆け出す。 「へぇ、本当に彼氏じゃなかったんだ」 再会を喜び合う二人の乙女に、トニエントは堂々と歩み寄るとにっこり笑って、 「さすが、可愛いリリさんは、ご友人も可愛らしいんだね」 と、さらりと言い、丁寧に自己紹介をしながらディミーに手を差出し握手した。何も知らないディミーは、にっこりと笑顔で自己紹介を返した。 「リリさんはメンタル科のアイドルなんですよ。カーナルさんもお勤め先でアイドルなんでしょうね。アイドルが二人も揃って眩しいなぁ。これから講習会なのに目が見えなくなりそうなので、僕はこれで失礼します。リリさん、また明日」 「お疲れ様でした」 リリは、引き攣りそうな薄い笑顔で頭を下げた。トニエントは颯爽と通りの向こうへ歩き去った。 「ちょっとちょっと、あのイケメンドクター、リリの何なの?」 ディミーは興奮している。こんなにコテコテに褒められた事は未だかつて無い。新鮮だ。 「何でもないよ、ミネルバさんの同僚ってだけ」 リリがそう答えた瞬間、ディミーの電話が鳴った。ゴセだった。ごめんねと言ってディミーは出る。 「何よ、邪魔しないでよ、あたし今日、仕事早く上がれて、今、久しぶりにリリに会ってるんだから」 電話の向こうで、ゴセが「リリは元気なのか」と訊ねたらしい。 「元気も元気、今だってね、超イケメンのドクターに言い寄られてたんだから!」 リリはびっくりして、ディミーの腕を引く。 「え、だって、リリの事、気に入ってそうだったじゃない?」 「そんなことないよっ」 「だってリリを、アイドルだ、可愛いって言ってたじゃない」 「ディミーの事だってそう言ってたでしょ、あの人はそーゆー人なのよ、平気で言えちゃう人なの」 「いやいや、あれはかなり、お気に入りと見たね! そーゆーわけでご心配なく、リリも私も充分楽しくやってます。じゃね!」 ディミーは面倒臭そうに電話を切った。 「兄貴ったら、仕事帰りにトイレットペーパー忘れんなだって。自分で買って来いっちゅーの!」 「もう、ディミーってば、ゴセさん、勘違いしちゃうよ」 「えー、さっきのイケメンドクター? もったいなーい、アタックしちゃえば?」 リリは肩で一息ついてから投げかけた。 「ディミー、タイプ?」 「え、あたし? うーん………。パスかな」 「でしょ、私もよ」 二人はぷっと噴き出すと、腕を組み「久しぶり、元気にしてた?」と喋りながら繁華街へ向かって歩き出した。 ディミーとリリは、オープンテラスのカフェでケーキとお茶のセットを頼んで再会を乾杯した。アレン達の壮行会以来だ。リリは、明るい屈託の無いディミーと過ごせて嬉しかった。絶望的な自分の事を、ほんの一時でも忘れられる。楽しい。 「ねえ、週末は何してるの? たまには会おうよ。今度の土日は予定入ってるの?」 週末はジョーの家政婦業だ。どちらかはフリーのはずだが、泊まってしまって結局両日ともジョーのマンション…という事が二度もあったので、家政婦業をしている間の週末は今の所、自由には出来ない。 「ありがとう、ごめんね、まだ覚えることとかたくさんあって、週末はいっぱいなの」 心がちくりと痛んだが仕方ない。 「そっか、偉いねリリ。じゃあ、一段落したらこうして会おうね。約束よ」 約束と言われて、リリは素直に応えられなくなった。 リリの様子がおかしい事に、さすがのディミーも気づいて、心配そうに訊ねた。 「どうしたの? 何かあったの?」 リリは、この心優しい女友達には言っておきたいと思った。 「ディミー、あのね、私、今、アルテミスだった時の記憶がないように、アルテミスに戻った時に、今のこと、忘れちゃってるかもしれないの」 「え…?」 「いつアルテミスに戻るかわからないから、ある日突然、私が約束を破って知らんぷりしてても、―――」 リリは言葉に詰まった。胸を手で押さえてぐっと涙を飲み込む。 「それは、意地悪してるとかじゃなくて、覚えてないからなの……。覚えてないなんて本当にごめんね。私、ディミーの事、本当に大好きなのに、忘れちゃうなんて信じられないんだけど―――」 ディミーは目を大きく見開いていたが、また言葉に詰まって、テーブルの上で固く握られたリリの拳をめがけて、手を伸ばした。 「大丈夫、あたしが忘れないから!」 ぎゅっと上からリリの拳を握って、ディミーは言った。 「リリがあたしを好きでいてくれた事、あたしがずっと覚えてるから」 涙が溢れ出したリリは、声にできずに、ただ頷いた。 「だから約束して。また会ってお茶しよう。もし、その日にリリが来なかったら、アルテミスに戻っちゃったんだって思えばいいだけでしょ? そんな事でリリを責めたりしないよ、信じてよ、リリを大好きなあたしを」 「………」 リリは小声にしかならなかったが「ありがとう」と答えながらディミーの手に顔を埋めた。 岸壁沿いの歩道のブロック塀にもたれて、とっくに暮れてしまった夜の海を眺めながら、リリは先日の記憶喪失中に結婚した夫婦の事を、大まかに話した。アレンと自分に重ねてしまった事、そしてもう二度と、あんな事はしたくないと強く思った事を、ぽつりぽつりと打ち明けた。 「そうだったんだ……」 ディミーは静かに聞いてくれた。リリの気落ちが落ち着くのを待って、ディミーはそっと言った。 「だからって、リリが今、誰かを好きなら、その気持ちを抑えちゃだめだよ?」 「………」 「だめだよ。さっきあたしに話してくれたように、その人にも話しておけばいいと思う。そんなの嫌だって離れてくようなら、まあ、それまでのヤツだったってことでさ、全部ひっくるめてリリのコト受け入れてくれる人かもしれないじゃない? 勝手にリリが一人で決めつけてさ、本当は生まれたはずの愛を摘み取ってしまうのは、相手の人に対して失礼だと思うよ、あたし」 「………失礼…?」 「うん。だって、相手のヒトも、リリの事好きなのかもしれないじゃない? 相手にも考えたり選んだりする権利ってあるでしょ?」 ディミーの言葉は、暖かく力強く沁み込んで来た。そうなのかもしれない…と思いたくなる。本当にそうだったら、どんなに幸せだろうか。 ミネルバもそう言っていた。「好きな気持ちを押し潰すな」「ジョーを諦めるな」と。 潮の香りはジョーを連想する。この海を渡って、ビドル島へ行った。セヴァ・ファームの島へ。それから、潮の香りの中で助けられた。唇を塞がれて。 潮風に吹かれながらリリは気付いた。ジョーのキスがただの手段だったと知った時に、悲しくて泣けたのは、ジョーが好きだからだ。 自分にとってジョーとのキスは、本当にキスそのもの。 ジョーが好き……。好き。 リリはもう素直に認めた。ミネルバも言っていたし、ディミーも言ってくれてる。好きでいいんだ。 ジョーに伝えたいとは思わない。だってジョーは私を好きではないだろうから。あのキスがそう教えてくれている。 でも、いいの。片思いだけれど、今は唯この気持ちに寄り添いたい。解放された“ジョーが好き”という気持ちに。 リリは高揚する気持ちのまま、 「うん、分った……。ありがとう、ディミー」 と笑った。ディミーはリリの笑顔が見られて、心底ほっとした。 「ね、御飯もいいけどさ、ちょっと飲めるお店に行かない? カサリナじゃない小洒落たお店」 「うん、連れてって」 「よし、行こう!」 二人はバスターミナルへと勢いよく歩き出した。 リリが帰りやすいようにと、移動のバスは一本だけにした。サンセットシティの湾沿いに降り立った二人は、外見で選んだ店に入って行った。 店内は壁や床がストライプに青白く発光していて、どことなく幻想的だ。カサリナにはない洒落た雰囲気がいい。ディミーは念のために、店の奥の方へ進んだ。万が一、リリをアルテミスだと騒ぎ出す客(しかも酔っぱらい)がいたら、自分だけではリリを守れない。なるべく人目は避けた方がいい。半地下になっているフロアへ降りると、大きな変形テーブルが一つあるだけで、すでに男が数人、座っていた。相席なんて有り得ない、と、踵を返しかけたディミーは、はっとして振り返った。 「ニック?!」 変形テーブルに座っていた男達が一斉に顔を上げた。 「やだ、お揃い?」 チーム・ハザウェイが並んでこちらを見ていた。リリは心臓が飛び出そうになってしまった。青い光を背に受けたジョーがこちらを見ている。ジョーも驚いているようだ。ぽかんとリリを見ている。そして、ケンとメッカとニックはと言うと、同時にはっ!と息を呑んで、ディミーの横に立っているリリを見たまま固まった。 「なんでよ〜、すっごい偶然ねぇ! あたし達、行き当たりばったりで入って来たのよ」 ディミーだけが自由に動き喋っている。しばらく一人で騒いでいたが、はたと思い直し、 「ね、これじゃカサリナと同じになっちゃって、ガールズ・トークできないから、違うお店に行こうか」 ディミーの言葉を聞いたケン、メッカ、ニックが、引き留めねばと一斉に僅かに腰を上げた瞬間、彼女はいきなり背後から首根っこを掴まれた。 「なぁ〜にが、ガールズ・トークだ! あれからもう4時間経ってるじゃないか。もう充分だろ! 座れ座れ! ほら、リリも突っ立ってないで歩いて歩いて!」 すでに酔っぱらっているゴセが、ぐいぐいと二人を押した。 「何よ、兄貴もいたの?」 「そう、すっごい偶然だなぁ。いや、さすがと言うべきか! 何しろこの店の名前、引力って言うんだぜ、知ってた? ちゃんと見て入って来た? 俺なんか、名前に引き寄せられて入って来てみたら、ここにチーム・ハザウェイが居たってわけよ! なぁ〜?!」 確かにグラスも皿も五人分ある。強引にテーブルまで押されながら、ディミーはジョーに訊いた。 「でも、あたし達お邪魔じゃない?」 ディミーの問いかけにジョーは我に返った。それまでずっとリリを見ていたのだ。 「え、あ、や、別にオレ達は…」 その、あまりにジョーらしくない返答ぶりに、ケン達はますます固まる。昼間のあの恋愛相談が生々しく蘇る。そしてこの、目の前のジョーの狼狽ぶり。一見、澄ました顔をしているので、ゴセなんかには分らないだろうが、チームメンバーには痛いほど良く判る。きっと今、ジョーの心臓はバクバクだ。 なるほど、ケンの言っていた通りだ。確かにジョーはリリに本気で惚れている! メンバーの心に火が付いた。こんな絶好のチャンス、逃しちゃなんねえ! 力にならねーと! 「なーに言ってんだよ、ディミー。邪魔なわけないだろぉ? 座れよ、一緒に呑もうぜ」 メッカが大袈裟にも思える口ぶりで答えた。 「え、そう? 本当に?」 「ディミーもリリも、俺たちの引力で引き寄せちゃったみたいだからなぁ。なあ、ジョー」 メッカ、軽快にラブジョークを放つ。も、滑る。 「そそそ、俺もね、引き寄せられちゃったの」 まったくお呼びでないゴセが可愛く反応した。 「ほんと、邪魔じゃないよ、座りなよ」 ケンはリリを見ながら声を掛けた。リリはケンを見て、ちらりとジョーに視線を移して、すぐにまたケンを見た。 リリは、自分の顔は真っ赤だろうと焦っていた。恥ずかしい。たった三十分ほど前に自覚したジョーへの気持ちが胸一杯に暴れている。生まれたてのぷるんとした柔肌が、いきなり熱風に晒されているような、そんな感覚だ。このままここにいるのは無理かもしれない、心臓がドキドキし過ぎて持たないかも…と弱気な反面、会えるはずの無かったジョーに会えた喜びも大きく、じゃサヨナラと立ち去る勇気が湧かない。 二人は決め兼ねていたが、さっさとゴセがテーブルの上の呼び鈴を押していたので、店員が二人分のコースターを持ってやって来てしまった。 「じゃ、兄貴にご馳走になーろおーっと」 ディミーは観念した。リリの腕を取って、自分がゴセの隣に座り、リリは気を遣わないようにと端に座らせた。しかし、その場所は、ジョーの真正面になる。 一瞬、二人の視線が交錯する。すぐに視線は外されたが、チームメンバーは密かに大興奮した。 「なになに、どうしてジョー達はここに来たの?」 「あー、本当たまたま」 ジョーの言葉の短さを、ケンが笑顔でフォローする。 「店の名前には気付かなかったなぁ、引力だったんだ。ゴセに続いて、ディミーとリリを引き寄せてくれたんなら、俺にはヒイナを引き寄せてくれるかな〜なんちゃって〜」 「いよ、このリア充! かみさんに会いたきゃ、家に帰れ! でもまだダメ! 呑もう!」 ゴセが拍手をしながら叫ぶ。 「ちょっと、ここはカサリナじゃないんだから、もっと静かにしてよ」 ディミーがゴセをたしなめた。 「お、そーだ、リア充と言えば、ここにもリア充になりそうなのが」 チームメンバー全員がどきりとした。なぜ、ゴセも知っているのだ?!と。しかし、 「リリなだけに、リリ充? なんつってー」 ゴセは自分で言って大受けしている。ジョーとリリの事ではなかった。 「うわ、ダジャレ、くっだらない」 運ばれて来た自分とリリのカクテルを受け取りながら、ディミーは思い切り呆れた。 「じゃ、お邪魔します」 ディミーはそう言って、グラスを上げた。リリもそっと上げる。 「おう! 引力に乾杯ー!」 メッカが殊更張り切ってグラスを上げたのに釣られて、全員がグラスを上げた。 リリの飲み物がカクテルだと知って、思わずジョーは声を掛けた。 「おー、ボーズ、ンなの飲んで、酔っぱらうなよ」 『ジョーとリリのやり取り』の火蓋が、唐突にジョーから切って落とされ、メンバーは密かに色めきだった。いきなりジョーに話しかけられたリリは咽てしまった。メンバーの意識が大集中しているとも知らずに、ジョーは言う。 「ほーら、やっぱ、無理してんじゃねーの?」 ハンカチで口元を抑えて、ジョーの二発目をやり過ごすと、リリも反撃した。 「急に言われて咽ちゃっただけ」 ケンもニックも、ジョーのひねくれた心配の仕方に悶えそうになった。メッカだけは、生のやり取りに目を輝かせている。 いつも通りの強気なリリの返答に、正直ジョーはほっとした。最後に見たリリは、青い顔で昏睡していた。 (それにしても…) と、ジョーはしみじみと再認識する。 (めちゃくちゃ可愛いじゃねーか……) ふいに現れた時の、ディミーと並んで驚いて立っていた姿はいつもと違って見えた。それもそのはず、ジョーと会う時はバイクがらみが多いのでどうしてもパンツ姿が多い。今夜のリリは仕事帰りなので、首元に淡い橙色のマフラーを緩く巻きつけただけで、街中用のハーフコートに膝丈のスカートという姿だった。 あんなに可愛くちゃ、もしかしてナンパされたんじゃないか…などと悶々と考えていたジョーは、リリの顔が赤い気がして、まじまじと見つめた。 熱がぶり返したりしてるのでは…? と急に心配になる。角を挟んで最も近くにいるディミーに「気付いて確かめろ」…と、密かに念を送るが届くはずもない。 我慢できずに、ジョーは自ら仕掛けた。 「ボーズ、顔が赤いぜ? もう酔ったのかよ? それとも熱?」 「え?」 ディミーがリリのおでこに手を当てた。よし!とジョーは胸の中で拳を握った。リリはディミーににっこり微笑んで言った。 「大丈夫よ、熱なんてないから」 「うん、熱くない。お店の中が暑いもんねぇ!」 ディミーは自分も暑いと言いながら掌をひらひらと泳がせた。自分の顔が赤い原因を分っているリリは、ますます赤くなる。 熱ではないと分り安心したジョーは、しかし彼女が酔っぱらってしまうのではという心配が消えず、つい口が滑る。 「お子ちゃまはジュースにしろよ、ジュースに」 「もう! 私は、おちょちゃまじゃ―――」 反論しようとして、リリは噛んでしまった。恥ずかしい。思わず俯く。 チーム・ハザウェイの全員は、俯くリリの可愛さに瞬時に化石化した。 (こんなにこの子は可愛かったっけ?)と、ジョーの恋の相手なのにドキドキしてしまう。 「ジョー、ずいぶんリリに過保護だな〜、リリはもうおちょちゃまじゃね〜んだぞ〜、なぁ〜?」 酔っぱらいゴセがガハガハ笑いながら言ったので、メンバーの硬直は解けたが、ジョーはしばらく人形のごとくぎくしゃくとしか動けなかった。当然口数は、ほぼゼロだ。もっと二人のやり取りを見たいメッカは、ここで一肌脱ぐ決意のもと、いつも以上に饒舌に話しかけた。 「なあ、俺、まだリリの制服姿って見た事ないんだけど、白衣の天使なの?」 今度はジョーが咽た。確かにメッカは直接リリの制服姿は見ていないだろうが、話をしたことがあるじゃないか、リリは受付だから白衣ではないと。 (どうした、メッカ、酔ってるのか?) メッカの真意など知る由もないジョーには不可解な言動だ。 「いいえ、私はナースじゃないので普通の制服です」 当然リリは答えた。 「何々? やっぱり男のヒトって、白衣の天使に憧れるの?」 ディミーがニヤニヤして訊く。 「そりゃぁなぁ。やっぱ、天使ちゃんでしょ」 「うっわー、メッカ、だめよ、もうおじさん入っちゃってる!」 どっと沸く笑い声の中、メッカが「俺のどこがおじさんなんだよー」と吠える。 「よし! 今度みんなで、病院へ天使ちゃんを拝みに行こう!」 意味不明なゴセの提案。 「そしてみんなリア充になろう!」 頑張れゴセーとケンが棒読みで言う。 「あ、そうだよ、リリ充、あのイケメンドクター、どうするんだ? 言い寄られてるんだろ?」 妹との会話を思い出したゴセが、リリに振った。 「え?」 リリは何のことかすぐに分らず、きょとんとしてゴセを見た。先にディミーの方が理解した。 「ああ、あの超イケメンドクターね! そうよ〜、もうね、リリのこと、アイドルとか言っちゃってねぇ〜?」 ニックは、自慢気にぺらぺら話し始めた幼馴染の口を、出来ることなら接着剤で閉じたいと思った。しかしメッカは敢えて食いついた。ジョーの闘争心を煽るつもりらしい。 「へぇ〜? リリ、病院でモテモテなのか?」 「アイドルで、可愛くて、お気に入りっぽいとか、おまえ電話口で言ってたよなぁ」 ゴセは何の計算もしていない。ただ本当の事を言っているだけである。 リリが病院の中で人気がある事を、とっくに知っているケンはハラハラしていた。ジョーだってそんな事は知っている。今更である。しかし、実際にリリ本人にアプローチして来た奴というのは、ちょっと違う。しかも、超イケメンドクターとは。 「違います、その人は本気でそんな事言ったんじゃなくて、ただからかってるだけなんです、ミネルバさんの同僚なだけですから」 リリが必死で言えば言うほど、ゴセとメッカは囃し立てる。 ジョーは、絶対にミネルバから訊き出さなければと内心烈火のごとく燃えていた。 「そう言えばさ、ジョーは運命の女、まだ探しに行かねーの?」 突然ゴセの矛先がジョーに向いた。 ジョーの前で、他の男との話を冷やかされて、いたたまれない気分に陥っていたリリは、ジョーの運命の女という言葉にドキリとして顔を上げた。思わずジョーを見ると目が合ってしまい、リリは慌てて伏せた。 焦ったのはジョーとチームメンバーだ。リリの前でその話は勘弁して欲しい。 「おまえが言い出したの、あれ、アレンがワッチの店に行く前だから、もう3〜4か月たってるじゃん。レースが終わったら探しに行くとか言ってたよなぁ。なぁ、連れて来いよ〜」 リリは、顔を上げることが出来ずに、全身を耳にして聞いている。メッカが大声で反撃する。 「いや、運命の女なんてのは、所詮、夢の話だよ。やっぱ、リアルじゃなきゃ。な? そうだよなぁ!」 チームメンバーが「そうだよ、リアルだよ」「遠くの幻より近くの生身だ」等、ハイテンションで追従した。 「案外、もう近くにいるかもだしな!」 メッカは渾身の止めを放ち、さあ、これでリリの反応はどうだ?! 頬を染めてもじもじしていたら、もう決まりだ! と思いながら彼女を見たが……俯いていて表情が良く解らない。 一度聞いてしまった『運命の女』の存在は、リリに大きなショックを与えていた。ジョーにそんな人がいたなんて。 しかもジョーは一言も否定しない。それが、どれだけジョーにとって大切な女性なのかを語っている。 そうだったんだ………。 つい一時間ほど前に自覚したばかりの恋心は、両想いなんて望んでいなかったけれど、こんなに早く結末を迎えてしまった……。 リリは口をきゅっと結んで、泣き出したい気持ちを堪えた。 テーブルを挟んだ真正面で下を向いたままのリリ、彼女を見ながらジョーこそ泣きたい気分だった。だが、リラの事を簡単に否定することもできない。否定はしないが、ゴセに言われるままに「探しに行く」とは言えない。 探しには行かない。オレはリリのそばにいると決めたのだ。 だから、ゴセのいう事なんかもう聞かないでいてくれ…と切望しながら、ジョーはちらりちらりとリリを見ていた。 その時、リリがぴくっとして手首を確認した。電話がかかって来たらしい。リリはそっとディミーに断り、するりと席を立って階段を上がり通路の方へ姿を消した。 しばらくゴセが一人で盛り上がっていたが、ふと、リリがいない事に気付いて、 「あれ、リリは?」 と妹に訊ねた。 「ん? ああ、仕事の電話みたい」 「仕事? あのイケメンドクターか? そうだろ!?」 「えー、違うでしょ?」 「いやいや、そうだ! そうに違いない!」 チーム・ハザウェイに重い空気が流れる。黙って酒を流し込む。ジョーは煙草に火を点けた。すぐにリリは戻って来た。 「何、デートのお誘い?」 悪気のないゴセが一番に言う。リリは一瞬「え?」という顔をしたが、 「いえ、まさか」 と薄く笑って着座しながらディミーに小声ですまなそうに言った。 「ごめん、ナースチーフからだったんだけど、私ちょっと病院に戻るね」 「え? 今から?」 「うん、書庫のロックを忘れたって」 「えー、そんなの自分で掛けに来ればいいじゃん」 「寮の方が病院に近いから」 「だって今は寮にいないのに」 ゴセが制した。 「まあ、勤めてると理不尽なこともあらぁな。しゃーない、しゃーない」 バッグを持って立ち上がったリリは、皆に向かって頭を下げた。 「ちょっと用が出来たので病院に戻りますね、じゃ、ごめんなさい、お先に」 チームメンバーの失望は大きかった。まさにメッカが「ジョー、送ってってやれよ」と言おうとした時、煙草をきゅっと消したジョーが立ち上がった。 「ボーズ、送ってってやる」 「え…」 リリは驚いてジョーを見た。 「そ、そうだよな、リリ、すげー方向音痴だからな、それがいいよな」 ケンがすかさず盛り立てる。 「え、大丈夫よ、バス1本だもん」 リリは慌てて言ったが、ジョーは煙草やライターをポッケにねじ込み、ジャケットを掴むと離席した。 「みんなはゆっくりやってってくれよな。また明日」 リリの横を通りながら、 「行くぞ、おら」 と声を掛ける。躊躇しているリリに、ディミーがにっこりして言った。 「送ってもらっちゃいなよ、その方が私も安心」 「…でも……」 「今日は会えて嬉しかった。また会おうね!」 そうウインクをして、すでに見えなくなっているジョーにも向かって、 「ジョー、よろしくね〜」 と掛けた。ディミーの言葉を合図に、メッカもニックも「お疲れ〜」と明るく送り出す。 ディミーに手でぐいと押され、向きを変えると、階段を数歩上がった所でジョーが待っていた。 現金な自分にため息が出る。つい今しがた、悲しい思いをしたばかりなのに、今の状況が嬉しくなっている。もうジョーは引かないだろうし。リリは改めて皆に一礼すると、ディミーに手を振ってジョーの方へ歩き出した。 店のドアを開けると、冷たい空気に頬を撫でられて思わず首が竦む。前に立っているジョーがジャケットの襟元から、下に着ているトレーナーのフードを引っ張り出して被りながら言った。 「バス1本だから大丈夫とかほざいてたな。じゃあ、どっちだ」 「……大丈夫だもん」 左へ歩き出す。正解だ。ジョーもおとなしく付いて来る。 「合ってるでしょ。ねえ、本当に大丈夫だってば。みんなと呑んでてよ」 言い終わらぬうちに、ぐいと腕を捕まれ、引き寄せられた。一本目を曲がり損ねていた。 「あ………」 さあ、これで、送る意義が出来たと言わんばかりのジョーの呆れ顔。 「じゃあ、…バス停まで送って下さい…」 夜8時。行きかう人は仕事帰りが多く、家路を急いでいるか、食事を求めて店を物色しているかだ。急に立ち止まったりする人を避けながら歩く。はぐれそうなので手を繋ぎたいところだが、それすら意識してしまってジョーは手を差し出せずにいた。そもそも、今までの女どもは、ジョーの腕に勝手にまとわり付いて来たので、ジョーから何かをした事は皆無だ。 そうだ、こいつは歩幅が小さかったっけ。 先日泊まらせた夜、ソファから寝室へ移動した時の、後ろから付いて来る小刻みな足音を思い出した。ジョーは、ペースを落とした。肩越しに振り返ると、風邪に吹かれている髪が見えた。 大通りへ出たジョーは、バス停の手前で車道を確認して手を挙げた。一台のタクシーが引き寄せられるようにやって来た。 「乗れ」 「え、ちょっと、」 まごまごしているリリの背を押し込むと、自分も乗り込み、病院の名を告げた。バス停が遠ざかる。 「ジョー……」 「バスかったりーじゃん」 今夜、こんな展開になるとは思ってもいなかったので、海賊ジョー丸出しなまま、バスに乗るのは到底避けるべきなのだ。 アレンもそうだったが、ジョーも普段は何もしない。自分を偽るのはバカバカしいし、何より面倒くさい。 だが、リリのためにはあっさり変装し、細心の注意を払う。彼女に迷惑がかからないようにと。 そんな事など知らないリリは、 (疲れてるなら無理に送ってくれなくても大丈夫だったのに……) と申し訳なく思う反面、こうして一緒に居られる時間が嬉しくて仕方ない。 「ディミーと会ってたって?」 とジョーが訊いた。 「……うん。ディミーも私も、早く仕事が終わって……。ディミーが連絡くれたの」 「そっか。で、ガールズ・トーク?」 ジョーは笑っている。 そのトークで、あなたへの気持ちを解禁したんだから…と内心思いつつ、 「そうよ。へん?」 「いや。ケーキ美味かったか」 「……ど、どうしてケーキを食べてたって決めつけてるのかしら?」 ズバリ言い当てられて、恥ずかしいけれどくすぐったい。 「美味かった?」 「……そりゃ、美味しかったわよ?」 「じゃ、今度そこ連れてけ」 「え……」 「美味いケーキに付き合ってやる」 顔がにやけてしまうのを、リリは必死に堪えた。 「コーヒーも美味しかったよ」 「いや、ケーキには紅茶だろ」 「そお?」 ジョー的には、リリ以外のコーヒーは全否定なのだ。 「…分ってねぇなぁ〜」 と言葉にしてみるが、無論リリには真意は伝わらない。 「組み合わせのセンスがなくてすみませんね。じゃ、ジョーは紅茶でどうぞ。でも、そうね、確かにいろんなフレーバーティーがあってね、」 楽しそうに話すリリを見ながら、ジョーはとりあえずは安心した。そしてディミーに感謝した。 タクシーは病院のタクシー乗り場まで乗り入れた。料金を払ったジョーが降りて、もそもそとリリも降りる。一般の出入り口は閉まっていた。ジョーは夜間救急外来口へと歩いて行く。 「夜の病院って、やっぱ出る? おまえ、見た事ある?」 にやにやして言うジョーに、リリはもう「どこまで来るのか」とか野暮なことは訊かない事にした。 「ないわよ。そんな遅くまでいたことないもん」 (ああ、そうか、この間は眠ってたからな) と、ジョーは密かに思いながら、薄暗い廊下をメンタル科へ向かって歩いて行く。 「ジョー、すごいね、よく分るね」 「ん?」 「だって、毎日来てるわけじゃないのに。しかもこんな、昼間とは全然雰囲気違うでしょ」 ジョーはぷーっと大袈裟に噴き出した。 「な、何よ…」 「じゃ、おまえは毎日来てるのに、迷っちゃうの? 夜ってだけで?」 「迷わないわよ、バカなこと言わないで」 ぷいとむくれたリリは、ちらりと周囲に視線を飛ばして、誰も居ないのを確認すると、堂々と 「ラス・ポウナ!」 と、ジョーに言った。ジョーは笑いを飲み込む。ちょっとの間考えていたが、やがて言い返した。 「ラス・ポウナ」 リリは驚いた。初めて反撃された。むっとする。悔しい。ちょっと考えてジョーに訊ねる。 「ヘッシュ語で“超”ってなんて言うの?」 「超? 「そう、超。すっごい、とかの超」 「……ルォ」 「ロオ…?」 「ルォ」 何度か口にして、ジョーのダメ出しがなくなると、リリは自慢げにジョーに向かって言い放った。 「ジョー、ルォ・ラス・ポウナ」 そう来ると分っていたが、面と向かって言われると、かなりの破壊力だった。一気に脈拍が上がる。きっと顔も赤いに違いない。 ―――超愛してる、かよ。 「そりゃー、こっちの台詞だ。ルォ・ラス・ポウナ、ラツィーナ・マーディ」 夜の病院の無人の廊下を歩きながら、薄暗さに手伝ってもらってジョーは言う。 「今、新しい言葉、足したでしょ。ラチーナ……って、何?」 リリが食いつくが笑ってごまかした。 「超バーカ、ボーズ。って言ったんだよ」 リリは怒っているが、ジョーは気持ち良かった。本心を口にするのは、こんな良い気分なのか…。 だがそれは、拒絶されない事が前提にある場合に限る。 ―――超愛してる、オレの愛しい人。 こう言われたと知ったら、こいつはどう思うだろう……。 とたんにブルーになるので、その先は考えないで歩いた。 診療室の前に来ると、受付カウンターには鉄格子のようなシャッターが下りていた。そのパイプの向こうで、ウインターコスモスが一輪静かに立っている。ジョーはちらりとそれを見て、月曜日と変わらないと思いながら、リリに言った。 「まだ咲いてるんだ」 「え、あ、うん、元気でしょ。奥にも飾ってるんだけど、そっちも綺麗に咲いてるよ」 「ふう〜ん」 もちろん、飾られている事は知っている。月曜の夜にミネルバと話しながら見た。でも、倒れたリリの元へ来た事は伏せて貰っているので、見たとは言えない。でも、彼女に嘘は付きたくないので当たり障りのない言い方をする。 カードキーでドアを開けて室内に入るリリについて、ジョーも入った。月曜の夜と同じ場所に花瓶はあった。今夜は悲しげには見えないが、若干元気がない。でもよく持っている方だ。花を大事にする心がけはジョーとしては外せない。リリはまめに世話しているようだ。満足する。 「はーい、終了しました」 明るい声で言いながらリリが振り向いた。 「あ? もう?」 「うん、だってロックするだけだもん」 そう言って、彼女はポンポンと書庫を叩いた。 二人は診察室を後にした。暗い静かな廊下をそっと歩きながら、ジョーが小声で言った。 「なあ、なんか聞こえねぇ? あっちの方から…」 そう言ってジョーはリリの肩越しに廊下の奥を指さした。 「………。何も聞こえません」 ジョーの企みに気付いて、ムッとしてリリは返した。 「いや、するって、ほら、」 「しないってば」 「しっ…!」 ジョー迫真の演技に押されて、うっかり指さす方を見てしまった瞬間、闇に沈んだ廊下の奥からゴトッという鈍い音が僅かにした。 リリは、飛び上がらんばかりに驚いた。一瞬にして体が強張り、暗闇を凝視する。怖いのに視線を外せない。が、すぐに光の筋が現れ、太くなった。ドアが開いたのだ。影が一人出て来ると、ドアはまた閉まり、廊下は闇に呑まれた。ゴトッという音の主はその闇の廊下を歩いて、突き当りを曲がって消えて行った。 「ちゃんと人だったじゃん!」 リリは脱力して怒っている。 「いや、あれ、先週死んだおっさんなんじゃね?」 「え?」 「自分が死んだ事、わかってないじーさんとかさ、いつも通りに点滴ぶら下げて歩いてたりしねーの?」 「………」 「空き部屋のナースコールが鳴るとか、到着してドアが開いたエレベーターが無人だとか」 ジョーが言い終わった瞬間、リリの横の壁が「リン…」と鳴った。エレベータのドアである。控えめで柔らかなはずのその音は、しかしジョーのせいで不気味な闇と化している静かな廊下に突然湧いたので、恐怖の音にしか聞こえない。脱力していた体が再び強張った。見つめている先でエレベーターのドアが開き、照明で明るい庫内が暗闇の壁にぽかりと浮き上がったが、誰も乗っていない。 「うわ、マジか」 とジョーが呟くと同時にリリがしがみ付いて来た。ジョーにとってはエレベーターの無人より、リリが飛び込んできた方が驚きだ。でも単純に、密接度が嬉しい。 「何びびってんだよ、そこのおばあさんがボタン押したから止まったんじゃん」 リリにそっと囁く。もちろん嘘だ。誰もいない。しかし哀れなリリは必死に居もしない人影を探す。自分だけが見えないのかと、いよいよリリの恐怖心は爆発しそうになって、ジョーの腕に強く顔を埋めた。 「見えない、どうしよう」 泣き声交じりに小さく喚く。こんな子供だましの嘘にころっと引っ掛かって泣きそうになっているなんて可愛い過ぎる。ジョーの『好きな子は苛めてしまう』気質がむらむらと疼き出す。 「お前の知り合い? 会釈してるぜ?」 「え…」 良くも悪くも素直なリリは、疑う事など全くせずに顔を上げた。恐る恐るエレベーターを見る。 (亡くなっても私に会釈してくれているのなら、無視しちゃいけない!)と一生懸命に凝視してみる。だが当然、誰も見えない。いよいよドアが閉まり始めると、リリはぎくしゃくとエレベータに向かって頭を下げた。ドアが閉まって廊下が闇に戻ると、ジョーを見上げてリリは囁いた。 「間に合った? 患者さん、分ってくれてた? ね、どんな人だった?」 ジョーは耐え切れずに噴き出した。そして愛おしさも抑えることが出来ずにリリを思い切り抱きしめた。 突然ジョーに抱きしめられてリリの心臓は更に跳ね上がり痛いほどに激しくなった。そんな事はお構いなしにジョーはギューギューとリリを抱きしめ揺れながら笑っている。 「ちょっと………ジョー?……… 」 どうしていいかわからず揺れているうちに、やっと気づいた。 自分には、見送った患者などいない事に。これは担がれたのか……? ジョーが笑っているのもまんまと騙せたから? 「ジョー、嘘言ったのね?! ひどい!」 「おまえ、誰もいないのに、頭下げてっ――」 笑ってしまって言葉にならないジョーの腕の中で、リリは文句を並べながらもがいた。しかしジョーの腕は一向に緩まず、がっしりとリリを抱き込んだまま揺れている。 (そんなに私の騙されっぷりが愉快なのかしら……) ジョーの本心など知らないリリは、抱きしめられている理由がそれしか思い当たらない。 でも初めてである。切羽詰まった危険な状況で助けるためなど必要に迫られているわけではないのに、こうして抱きしめられているのは……。 パニックの嵐の中、心臓は激しくドキドキして、頭の中が痺れて蕩けてしまいそうだ。意識して踏ん張っていないと、ジョーの腕の中を味わうために黙ってしまいそうになる。 このままジョーの胸にくっついていられたらいいのに。ジョーの引力が私を捉えて離さなければいいのに。 そう考えてしまいながら、それらの強力な甘い引力にリリは一生懸命に抵抗した。 「ジョーの意地悪! ラス・ポウナ!」 こんな状況でも、愛してるなんて言われると嬉しい。意味が違っていても。 (いよいよオレは危ないヤツだ)そう思いながらジョーも腕の中の愛しいリリに言い返した。 「はいはい、ラス・ポウナ」 この期に及んで尚もおちょくられたと取ったリリは、自由にならない両手で拳を作り、わずかな隙間で一生懸命胸を叩きながら、何度もジョーに「ばか」と言った。そのたびにジョーも言い返す。 抱き合いながら小声でぶつけ合う「ラス・ポウナ」という音は、誰にも聞かれることなく暗闇に吸い込まれていった。 研修先から病院に戻って来ていたトニエントは、リリが長身の影と歩き去るのを柱の陰からじっと見ていた。 「彼氏持ちだったのか? ……いや、でも…」 歩く二人の距離感を敏感に感じ取り、おそらくまだ恋人未満だろうと判断した。メンタル科のドクターだけあって、なかなか鋭い。気付くのがもう30秒早かったら、抱き合って揺れているシーンだった。もしそれを目撃していたら恋人だと思って諦めたのかもしれないが、 「こりゃぁ、早く手を打たなくちゃな」 と顎をさすりながら静かに思案し始めた。 寮のエントランスが見える角まで送ると、じゃあなと言って帰ろうとしたジョーは、上着の端を掴まれて振り返った。 「ん?」 リリは眉をひそめて僅かに唇を尖らせて 「……責任、取ってよ」 と呟いた。 「……何の?」 本気でわからずジョーが訊くと、リリは信じられないと言わんばかりに目を見開いて言った。 「怖がらせたでしょっ?!」 「あ、」 理解した瞬間、思い出してしまって、また噴き出してしまった。抑えようとするが無理だ。ぶくくっと零れる。 「ほんとにひどいんだから……」 リリは恨めしそうに睨んでいる。笑いながらジョーは謝った。 「悪ぃ、悪ぃ、いや、でも、じゃあ、どうしたらいい?」 リリは俯いて、もじもじと呟いた。 「だから……部屋まで一緒に来て」 「え…でも………。誰かに見られたら、おまえに迷惑かかっちゃうし…」 「そんなの平気、大丈夫。今一人にされる方が大丈夫じゃない。部屋に入って電気付けるまで一緒に居て」 「怖がらせちまったのは悪かったけどさ、幽霊なんていなかったろ?」 「そんな言葉出さないで!」 ジョーの口を塞がんばかりに、リリは自分のマフラーをはずして、ジョーの鼻まですっぽりと巻いた。 「これでもう誰だかわかんないっと」 ジャケットの襟元から、下に着ているトレーナーのフードを引っ張り出して被り、その上から女物のマフラーをぐるぐると巻いて顔を隠している男は、海賊ジョーには見えないが、充分怪しい男には見える。 「……オレ、変質者?」 「うんもう、一緒に歩いてれば違うでしょ」 リリはぐいとジョーの腕を引いて歩き出した。 階段を上がる。二人の足音だけがそっと響く。 三階まで上がった時、突然目の前に人影が現れた。リリは息を呑んで立ち止まりジョーの腕をぎゅううっと抱き込んだ。人影はすれ違いざまに寒がりな長身男をちらりと見上げたが、そのまま階段を下りて行った。ジョーの腕を掴んでいた力が弱まる。 「寮の住人じゃん」 しかしリリは必死である。ジョーは、病院でリリをからかったことを後悔した。心底怯えさせてしまったようだ。 足早にリリは最後の階段を上った。ジョーの腕をがっしりと抱え込みながら、廊下を猛進し、自室のドアの掌紋鍵を一撫でして開錠すると、玄関内に雪崩れ込んだ。 後ろでドアが閉まる。自動で照明が灯った玄関でリリは呼吸を整えようと大きく息をしていた。 ジョーはまだ腕を取られている状態でそばに立っていた。引っ越しを手伝って以来の彼女の部屋にまた来ることが出来て、胸の高鳴りを抑えきれずにいた。 そんなジョーの心中など知らないリリは、当面の問題に立ち向かうためジョーに振り向いて、まだ乱れている呼吸のまま途切れ気味に懇願した。 「ジョー……、もうちょっと中まで………、お願い………」 「分った、部屋中の明りつけてやっから待ってろ」 「あっ、いやっ! だめだめ! ……一緒に、一緒に行くの…!」 ジョーが抜こうとした腕を、慌てて抱き直してリリは言った。 そうして、二人は全部の明りをつけて回った。狭い室内はあっという間に煌々と輝いた。ようやくリリは小さく礼を言ってジョーを解放したが、言いにくそうに俯いて 「もう一つ、お願いしていい……?」 「…なに?」 ここまでリリを怖がらせた負い目も手伝って、ジョーの声色は優しい。 「煙草……、吸っていって……」 「煙草?」 「一本でいいから、ここで…」 「……構わないけど…」 煙草なんてわざわざ吸わなくても、落ち着くまで傍にいてやるのに、と思って答えると、リリはぱっと笑顔を咲かせて、 「ありがと!」 と言うなりキッチンのカウンターから灰皿を取ってテーブルに置いた。煙草を吸わないリリの部屋で灰皿が出て来てジョーは驚いた。 「どうしたんだよ、これ」 「え? 買ったんだよ? …変? 可愛いと思ったんだけど…」 「……おまえ吸わないじゃん」 「私の旦那様が吸うでしょ」 この場合、旦那様とは雇い主という意味だとジョーも解っているが、うっかり勘違いした妄想は甘美だ。 「今、コーヒー淹れるから」 (オレが使うから買ったって事は「この部屋にオレが来る」もしくは「オレを招き入れる」と想定してたって事か……!) 嬉しい。にやけそうになるのを必死にこらえながら、キッチンへ声を掛ける。 「ここで吸っちゃっていいのか?」 「うん」 「部屋がモクモクしちゃうぜ?」 「いいの。ねえ、座って、ジョー」 コーヒーの香りが漂って来た。ジョーは素直に椅子に掛けた。煙草を出して火を点ける。紫煙を吐き出すと、リリの部屋の天井目がけてゆらりと昇って行く。 「せっかくみんなと呑んでたのに、私のせいでごめんね」 キッチンからリリが言う。 「いや、別に。あいつらとはいつも呑んでるし」 「でも……」 「いいんだよ、コーヒーにありつけたからな」 オレが一緒にいたかったからという一番の理由は言えない。 「豆、一緒だよ」 「おまえも気に入ってんの?」 「うん、おいしいから」 ジョーと同じコーヒーを飲んでいたいからという一番の理由は言えない。 トレイにコーヒーを乗せてリリが来た。白いシンプルなコーヒーカップは、二つとも同じだった。ペア…という訳ではないのだろう、同じカップを二つ買ったという感じだ。 (いや、当然だろ。ペアカップを買うわけないじゃんか!)とジョーは自分に突っ込む。ジョーの目の前でコーヒーの湯気をそっと吹きながら一口啜ったリリは、煙草の甘い香りを確認するように吸い込むと、満足そうに笑った。 「やっと、この世にいるって実感できた」 「さっきまであの世にいたのか」 「境目に居た感じだったの。誰のせいよ」 小さな唇が可愛く尖るので、ついからかってしまう。 「エレベーターのおばあさんのせい?」 「ラス・ポウナ!」 いい加減に本当の意味を言ってしまった方がいいのだろうか…心臓に悪い。 ただでさえ目の前のリリが可愛くて可愛くて、とてつもない努力をしていつも通りの表情をしているのに、愛してるなんて言われては、平静を装うのがとても苦しい。とうとう言葉を返せなくなった。 窒息しそうなジョーは、苦し紛れに自分に問いかけた。 (ちょっと冷静になれ。客観的に考えてみようぜ。可愛い、だろ? どこが?) 経験値の低いジョーは、泥沼に自ら歩を進める。 (まず、コイツはチビだ。可愛いのとは違うだろ、ガキみてえだよな。隣に並ぶと、いつも頭のてっぺんしか見えないっつーのはガキ要素だろ。その頭、髪の色は、まあ、いいけど、そうだな、色はいい。けどな、でも、短くてやっぱガキみてえだろ? 毬みたいで…まあ、面白いっちゃぁ面白い。手触りも、まぁ、良いかな。ほわほわしてんだよな。でも、可愛いのとは違うよな。次は目だ。目は…アメジスト…いや、アッシュがかった…バイオレット…笑うと三日月になって、びっくりすると真ん丸になって…くるくると良く動いて、まっすぐにオレを見てくる……) 観察しながら見ていたので、視線の合ったリリに見つめ返され、動けなくなる。そう、泥にがっちりと足を掴まれてしまったジョーは、立ち往生だ。自由になる目だけ動かし、視線を外して抵抗する。 (いや、待て待て待て。あのお子様体型はどうだ! 凹凸がなさ過ぎるだろ? やっぱでっぱりはなくちゃよ。こう、手から零れるぐらい―――) 指の間からはみ出る肉感の乳房を連想する。しかしそれは、すーっとしぼんで掌に収まってしまった。蓋のように乗っている自分の手に、小さな手が寄り添った。鎖骨の方へと視線をずらすと、小さな花びらのような赤い唇が「ジョー…」と切なげに動く。 ジョーは泥の中で我に返った。ありとあらゆる、まだ見た事のない妄想の姿のリリを、泥と一緒に放り投げて脱出を試みた。動悸は激しく、額の帯が汗ばんでいる気がする。 目の前のリリは、そんなジョーの葛藤も知らないで、いつも通りに見える。 (オレばっかり情けねぇな) これが俗にいう『惚れた弱み』というのだろうかと、ジョーはもがき続けた。 しかし、ジョーだけではない。苦しいのはリリも同じだった。 ジョーを好きだと認めてからまだほんの数時間だ。考えないようにしようと思っても、ジョーの顔を見るたびに打ちのめされる。 (ジョーったら本当に素敵なんだから…!) 両手を挙げて降参してしまいたい。運命の恋人を探しているらしいけれど、今は、今はここにいる。目の前にいる。私といる。私はちゃんとリリだし。 ミネルバやディミーのおかげで、今はただ、ジョーへの気持ちを素直に認めていられる。打ち明けようなどとは思わないが、好きだと思っていても良いのだと、自分を許せている。 幸せだ、と思う。月曜日の自分に比べたら何て幸せなんだろう。ジョーを好きでいて良いなんて。 しかも、あの唇は私の唇と重なった事がある。キスじゃなかったとしても、私にはキス。ジョーとしたキス。 キスの事を考えると、どうしても切なくなってしまうけれど、でも大切な思い出だ。 (大好きな人が、重ねてくれたんんだもん…) うっかりジョーの口元を見てしまい、慌てて視線を逸らした。 「こ、今度の週末は、どうしたらいいの?」 喋っていないと恥ずかしさに飲み込まれてしまいそうなリリに、ジョーは煙を吐き出しながら答えた。 「土曜日でいいか?」 「…うん、もちろん、どっちでも」 土曜日とは言いながら、家政婦に行った二回とも、そのまま泊りになって、結局両日だ。今度もそのパターンなのかしら…とリリの鼓動は駆け足になる。 「じゃ、土曜日な」 「うん」 「いつもの場所に9時な」 「はい」 二人とも照れ臭さを必死に押し殺して、何でもない風を装いながら約束した。 コーヒーを飲み干すと、煙草を灰皿できゅっと消してジョーは立ち上がった。 「じゃオレ、帰るな」 「あ……」 とたんにリリの眉毛が心細そうに下がる。テーブルの上の煙草を灰皿の横に滑らせてジョーは言った。 「やるよ。吸わなくても火つけるだけで煙出るから」 「え…」 「好きなんだろ」 自分を見下ろす真っ青な瞳に捉えられて動けない錯覚に陥りながら、思わずリリは答えていた。 「……うん…スキ……」 「…ん、オレも好きだ……」 自分を見上げる紫色の瞳に好きと言われて、ジョーもつい、応えた。 お互いに煙草の香りの事だと分っているが……。そうじゃなくて、自分への告白だったらどんなに……。 「ありがとう…」 耐え切れずに俯いて、リリは煙草を引き寄せた。 「おう、じゃな。ごっそーさん」 歩き出すジョーの後を、慌てて追いかけたが、 「ここでいい。顔出すな。おまえのマフラー、借りてくぜ」 玄関でそう言うと、さっきリリが巻いたマフラーを自ら顔半分まで巻いて、 「裏通りでタクシー拾って帰るから心配するな。もう寝ろよ、明日も仕事なんだし、酒飲んでるし」 そう言ってジョーは一人ドアの向こうへ消えた。ドアにピタリと耳を当てると、ジョーの足音が遠ざかって行く。 これからジョーは、一人でタクシーに乗ってマンションへ帰るんだ……。 裏通りなんてここからは見えないので、もうジョーの姿を見ることは出来ない。 リリは切なさに押しつぶされそうになった。テーブルの上の煙草を手に取る。 ジョーが持ち歩いていたので、箱がくだびれている。それすらも愛おしい。 引力という名の店で会えた。部屋まで来てくれた。でももっと一緒にいたい。 (いっそ、泊まって行ってと言えば良かった?) と弱気に考えるも、すぐに打ち消す。 (有り得ない、泊まる理由がないし。でも…) 引力がもう一度引き寄せてくれて、ジョーが戻って来てくれたら……と思ったが、ジョーの方も、ともすればくるりと方向を変えそうな程に甘く強い引力を感じながら、 (何でもねーのに、泊めろなんて有り得ないだろ!) と必死に抵抗して歩いていたので、今宵の引力はこれ以上二人を引き寄せられなかった。 |
||
| 第34話 引 力 END | ||
| <<TOP <<BACK NEXT>> | ||
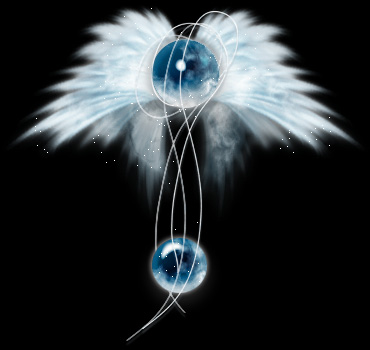
 ぺた ぺた |