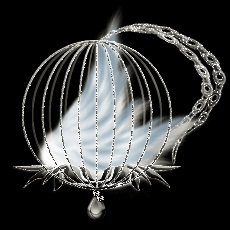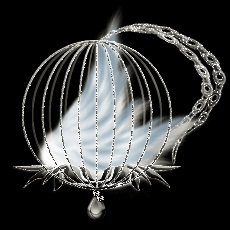|
想像していた通りブレイブアローのあちこちで、それは頻繁にふいに襲って来た。その度にアレンの心臓はどくんと跳ね、そのまま駆け足のリズムで脈を打った。
ワッチの店を後にしてから地球へ帰還するまでの甘い旅の痕跡は、ベッドルームはもちろん、無機質な廊下やブリッジにまで切なく残っていた。
今はもういない。アリーと呼んでいた恋人だったアルテミスはいない。
ミネルバの病院で活き活きと働いている女は、リリという別人なのだ。俺の知らない女なのだ。
数日後には土星までの長旅に出る。船の調整と共に、色々と整理しなければ。
そう分っていても溜め息ばかりだ。そんな自分に疲れてしまって、アレンはコンピュータ室へ入り床にしゃがみこんだ。寄りかかったコンピューターの壁が背にひんやりと冷たい。
――アレン、疲れてるな。
レッブが話しかけて来た。
「あぁ、ちょっと休ませてくれよ」
――休むなら、ベッドに入った方が、
「ここにいたいんだよ」
ベッドなんて思い出だらけで滅入るだけだし、何より、死闘を共に潜り抜けずっと一緒にいてくれたレッブのそばにいたかったのだ。
そう、レッブがまだ、ザナックの船だった頃からの付き合いなのだから。
後に『狂乱の月』と名づけられた月面居住地区内派閥闘争は、たったの二年で7基あったベースを壊滅させてしまった。
戦争終結直前にすでに戦争孤児になっていたアレンは、同じく戦争孤児になっていた幼馴染の親友ユウジとその妹カグヤと共に、最後の脱出船に乗り込んだ。ベース内は戦争により、動植物の生存する環境が失われ始めていたのだ。留まれば確実に死んでしまう。
「どんな船でも空へ逃げれば何とかなる、直に太陽系連邦局からの救助が来る」
それは根拠のない噂だったが、飛び立つしか生き残る道はなかったムーンベースの人々は、同じ人類を見捨てるわけはないと信じて月面を捨て暗闇へ浮上した。
やっとの思いで空へ逃げた民間船達は、しかし、政府要人が密航している容疑のため、あっさりと攻撃を受けた。防御用の砲台すら持たない丸腰の宇宙船ですら容赦なく沈められた。結局、宇宙へ逃げた一般人もほとんどが犠牲になった。まさしく狂った出来事だった。
自分達の乗り込んだ船が攻撃を受けた時、アレンとユウジはカグヤを守りながら、子供ばかりが集められた部屋の隅で丸くなっていた。着弾の衝撃はすさまじく、七歳のカグヤは泣き通しだった。大人たちの喚き声が廊下で飛び交っていたが、何か手伝いに出ようと思っても、カグヤがそばにいてくれと二人を放さなかったし、実際、専門教育を受けたわけでもない十二歳の少年が役に立てる事など無かった。
数時間耐えた船はかろうじて撃沈を免れた。
あれほどガンガンと響いていた衝撃音は止み、代わりに何かがショートしているバチバチという音だけが響く。
子供達は恐る恐るドアを開け、廊下に出た。焦げ臭い船内に人影はない。
「様子を見て来るから、皆、部屋の中で待ってるんだ」
年上の少年が三人、そう言い残して出て行った。
数十分後に戻って来た彼らの話は絶望的な内容だった。
どこもかしこも被弾しているらしく、あちこちの防御壁が降りていて、ブリッジにも辿り着けなかった事。サブブリッジのモニターに映されていた防御壁の先の画像達は、どこにも生きている大人の姿を映していなかった事。
「この船の中で生きているのは、多分、俺達だけだ」
子供達だけを乗せた船は、舵を取る事も出来ない難破船と化していたのだ。
「でもな、食料庫と酸素循環装置は無事だったから、助けが来るまで頑張ろう」
年長と言え、若干十五、六歳の少年たちは、年下の子供達を励ました。
不安でいっぱいのカグヤに「大丈夫だからな」とユウジは笑いながら言い続け、アレンもカグヤの頭を撫でてやった。
家が隣同士で生まれた日も近かったアレンとユウジはいつも一緒だった。アレンは三歳で父親を事故で亡くし母子家庭になってしまったが、ユウジのおかげで楽しく実りある幼少期を過ごせた。その親友の五つ年下の妹は、やはりアレンにとっても大事な妹のような存在だった。
カグヤを早く安心させてやりたい。
早く救助されたいと、船内の子供達誰もが切望していたが、太陽系連邦局の救助は来ず、いよいよ食料が尽きかけた頃、SOSに気付いて近寄って来てくれたのは巨大な戦艦だった。
窓外にみるみる接近してくる巨大な戦艦に子供達は怯えた。しかし、逃げることも出来ずに強制ドッキングされるのを息を詰めて見ているしかなかった。
ところが、船内に入って来たのは、まさしく救助の大人だった。
太陽系連邦局員ではない事は、接舷された船の外見と、目の前に立つ男の風貌で、小さな子供でも理解した。
部屋に入って来た男は、室内をざっと見渡すと
「なるほどな、応答がないと思ったら、おまえらだけだったのか」
と言った。無言で震えていると、
「こんな幽霊船で良く頑張ってたな。もう大丈夫だぞ」
と笑いながら、怖がるんじゃねーよ、助けに来たんだぜと更に笑った。
そして、男の部下らしき数人の男達に付き添われて、子供たちは巨大戦艦に移った。
巨大戦艦内にはたくさんのクルーがいて、エンジンが確かに動いている規則正しい頼もしい振動が艦内の空気を僅かに揺らしていた。
とっくにエンジンは停止し、惰性で漂っていた救助船では感じなかった感覚だ。
おどおどと歩く子供たちを、クルーたちは仕事の合間に振り返り、無言だったり笑いかけたり様々な歓迎ぶりだった。
食堂に集められた子供たちにたっぷりと食事をあてがいながら、先ほどの男は自己紹介をした。
「俺はザナック。この船の艦長だ。船の名前はブレイブアロー。でっかい戦艦だ。戦争するわけじゃねーがな。戦争って言やぁ、ムーンベースの内乱は終わったぞ。知ってたか?」
意味の分かった年頃の子供たちはスプーンを持つ手が止まった。カグヤ達、幼い子らの無邪気な食事の音だけがカチャカチャと響いた。
年長の少年が答えた。
「いえ…、知りませんでした…」
機能を失った救助船内で情報収取など出来るはずもない。
「だろうな。月面は全滅した。おまえらの帰る家はない、ってこった」
この言葉はカグヤにも理解できた。手を止めザナックを見ると、隣の兄を見上げた。
「おまえら、親とか親戚は?」
「僕達は…、みんな、孤児で……脱出も最後の船に何とか乗せて貰って…」
面倒を見てくれる大人のいなかった彼等は、脱出の手続きなどされておらず、なかばどさくさにまぎれての乗船だったのだ。
そして、彼等の先祖が月面に移り住んでからもう百年以上、一世紀を越えているのだ。ほとんどの子供は、月面以外の親戚など知らなかったし、どこかのコロニーにいたとしても付き合いの薄くなった親類の子供を引き取る確率は低い。
「分った。良く聞けよ。おまえらには二択ある。まず一つ目。孤児の施設に行く。俺が太陽系連邦局に掛け合って、おまえらをちゃんと引き取らせる。それは約束する、安心しろ。
もう一つな。船の中で仕事をしながら暮らす。つまり、この船のクルーになるって事だ」
子供達はじっと動かなかった。誰も何も言わなかった。
「すぐに決めなくていい、でもしっかり考えろ、自分の人生だからな」
「ま、待って!」
立ち上がったザナックを引き留めたのはアレンだった。
「ん? 何だ?」
「俺でも……、クルーって、俺でも、出来るの……? 俺、何も知らないし……」
「始めってのは誰だってゼロだ」
そう笑うと、いっぱい食えよと皆に言い残し、ザナックは食堂を出て行った。
展望ルームの窓外に広がる宇宙を背にして、壁に埋め込まれたモニターをアレンは見つめていた。複数に分断された映像は、各部署の様子を映している。どの場所でもクルー達が動いている。
「なあ、ユウジ、俺さ、」
「この船に残りたい、だろ?」
まさかの親友の言葉に振り向くアレンに、ユウジは笑った。
「俺も同じだよ」
「そっか!」
「うん!」
「こんなでかい船の乗組員なんてすっげーよな!俺さ、乗った時からワクワクしちゃってさ、すげーすげーって、もうとにかくこの船カッコイイって思ってて!」
「俺も!」
「ここで勉強させてもらってさ、俺、いっちょまえの船乗りになりたい!」
「アレン! なろうぜ、二人で!」
興奮している兄の服を引っ張って、カグヤが懸命に割り込んで来た。
「カグヤも一緒でしょ?」
「もちろんだよ!」
妹の頭をぐりぐりしながら、ユウジはアレンにも言った。
「艦長に言いに行こうぜ。それでカグヤの事は頼んでみる」
ザナックは、アレンとユウジがクルーの卵になる事を快く歓迎してくれた。そして妹の事までも
「チビだろうと女だろうと、仕事は山ほどあるさ」
と笑った。
どんな過酷な労働を強いられるのかとユウジは不安になったが、いざ館内での生活が始まってみると、カグヤに課せられた業務は、女性クルーの元、生活圏内の掃除や洗濯といった類の手伝い程度だった。
ザナックに拾われて一週間後には、子供達は太陽系連邦局に引き渡され下船して行った。四十名あまりの中で、ブレイブアローのクルーを希望したのはアレンとユウジとカグヤの三人だけだった。
後に知る事となるが、『狂乱の月』の戦争孤児で、こうして太陽系連邦局に保護してもらえたのは、実はこの子供達だけであった。何万人といたはずの子供達は、月面で、或いは脱出船の中で、人生を奪われて行ったのである。(ただ一人、アルテミスという名の少女が、ある経緯を辿って生き永らえるが、これは明るみに出ない真実である)
いかにこの派閥闘争が黒歴史であるか。廃墟と化したムーンベース群はそれから数十年に亘り放置され、亡霊を乗せた月はひっそりと沈黙のまま地球の上に浮くのである。
ザナックは、屈強の宇宙戦艦を持つ宇宙の『何でも屋』だった。
ブレイブアローの乗組員は八十名ほど。出身地も年齢も様々で、女性クルーも数人いた。
最年少はもちろんカグヤだが、次いで幼いアレンとユウジを、皆、それぞれの分野で育ててくれた。可愛がってくれた。
そうして二人はこの船の中で、宇宙船乗りとして逞しく成長して行ったのである。
それから五年経ったある日。
ヴィーナスエリアのとあるコロニーに、仕事の打ち合わせでブレイブアローは寄港していた。
非番の時間、カグヤが女友達(年配だが)と買い物に行くというので、町まで車で送った帰りに、ユウジは小さな湖を見つけた。
車を停めて湖畔へ下り、その美しい景色に深く溜息を付いた。贅沢に配置された緑の木々と水。青いスカイビジョンを湖面に反射させてきらきらと眩しかった。
ふと、すぐそばにうずくまる影に気付いた。少女が膝を抱えて座り込み、腕の中に顔を埋めて肩を震わせている。
こんなに美しい場所で、声を殺して泣いているらしい少女。
どうしたものかと考えたが、このままくるりと踵を返すのも不自然な近さだったので、ユウジは遠慮がちに声を掛けてみた。
「えーと……、どうしたの…?」
少女は弾かれたように顔を上げた。
そんなに驚かせてしまうなら声など掛けなければよかったと、すぐにユウジは後悔した。
しかし……。
目の前の彼女は予想通りに泣いていて、両の頬は涙で光っていた。止まり切らなかった涙が大きな青い宝石のような瞳からぼろりと零れた。
美しいと思った湖があっという間に霞んでしまう程の美しい瞳に見上げられて、後悔の念は消えてしまった。
「大丈夫…? 何か、俺にできる事ある?」
迷子なら送り届けてやれる、悲しい事があったなら話を聞いてやれる、そう思いながら、ユウジは頑張って微笑んでみた。
ぎこちないユウジの笑顔を少女はしばらく見ていたが、涙に濡れた睫毛を揺らして瞬きをすると俯いた。
「ありがとう…」
消え入りそうな小さな声がした。
悲しい声色だったのに、少女にぴったりの声だとユウジは思った。それきり少女は沈黙した。泣き声は聞こえない。泣き止んだのだ。ユウジはほっとしたが、これで立ち去るのも躊躇われた。少女にあっちへ行けとも言われていない。
「綺麗な湖だね。こんなコロニー、初めて見たよ。すごいよ」
少女は答えなかったが、少しだけ顔を上げ、視線を湖に移した。
「僕がここの住人だったら、自慢しちゃうね」
「……何て…?」
視線を動かさず少女は訊ねた。
「“とにかくすっげーから見に来いよ!”」
「………」
ちょっとの間を空けて、少女は呟いた。
「大雑把……」
「でも、俺の友達はこれだけで来るよ?」
「……ほんと…?」
「ああ、“マジで? 行く行く! ”ってさ」
「ふふふふ…」
少女の肩がまた揺れたが、それは笑いが漏れての揺れだ。ユウジは嬉しくなった。
「単純」
「そうだよ、単純だよ。すごい、楽しい、面白い、これが一番」
「……毎日、そればっかりだったらいいのに……」
彼女の言い方は寂しげだった。ユウジは切なくなった。
「最近、つまんないの?」
彼女は黙ったまま湖を見つめていたが、ふっとユウジを振り仰ぎ訊ねた。
「あなたは? 楽しい事あった?」
「すごい事はあったよ、たった今」
そう答えて、ユウジは湖を指さした。
「すごい綺麗な湖」
「この湖、気に入った?」
「言ったじゃん、自慢しちゃうって」
少女はまた、ユウジから湖に視線を戻した。湖面の反射を受けて目を細め、
「私も大好き」
と呟いた。しかしやはり悲しげだ。
「大好きなのに……もうこの湖を見られなくなっちゃうの…」
再び彼女の瞳から涙がはらりと零れ落ちた。ユウジは焦った。女の子に目の前で泣かれるのはカグヤで慣れているはずだが、勝手が違う。
「引っ越すの…?」
少女は答えずにまた腕の中に顔を埋めて泣き出した。
ユウジの頭に色々な言葉が浮かんだが、どれも不正解のような気がして口に出来なかった。慰める手立ての無いまま、彼女の横にしゃがんだユウジは、妹にするようにそっと彼女の頭に手を置いてみた。彼女はユウジの手を払うことなく、静かに泣き続けた。
「あの湖に…隠したの、昔…。ママの形見だった宝物…。パパが再婚した時に、捨てられちゃいそうになって、急いで私…ママとよく散歩に来たここへ隠したの……。ここはママもお気に入りの場所だったから……。それが…見つからなくて…」
ユウジは彼女の話を辛抱強く聞いた。
近々このコロニーを出て行くのに、母の形見を拾い上げようにも沈めた場所にないのだそうだ。沈めた物は小さな防水の箱らしい。数年のうちに魚に突かれたり微弱な波に揺られて湖底を動いたのかもしれない。
見たところ、湖水は良く澄んでいる。無論、コロニー内の人工の湖なので深度もたかが知れている。ユウジは立ち上がると、あっという間にTシャツを脱ぎ捨て裸足になり、彼女が気付いた時には湖に入っていた。
「止めて! ねえ、危ないわ、戻って来て!」
少女は立ち上がって叫んだ。
「大丈夫だよ。水が綺麗で底がよく見える」
ユウジは足に絡みつく水の流れを感じ、少しずつ奥の方へと進んで行った。
戻って来てといくら言っても、どんどんと深みへ進んで行く青年に、彼女はどうすることも出来ずに水際でおろおろするしかなかった。うっかり形見の事を喋ってしまった自分を呪った。会ったばかりの見知らぬ男の子に、何をぺらぺら喋っていたのか。
とうとう彼は泳ぎ始めた。足が着かないほど深いのだ。そして大きく息を吸い込んだかと思うと、飛沫をあげて湖面から消えた。潜ったのだ。彼女は静まり返った湖面を凝視した。永遠かと思われる程の時間が経過して、彼女が絶叫しそうになった瞬間、大きく飛沫を上げて彼が顔を出した。彼女は心臓が張り裂けそうになった。しかし彼はすぐにまた湖面から消えてしまった。そんな事を何度か繰り返し、彼女が心配でヘトヘトになりかけた頃、ようやく彼は岸に戻って来た。
「これ?」
荒い息遣いのまま、ユウジは箱を差し出した。違うなら引き返して再び捜索しようと思っていたのだが、その箱こそが、十年前に六歳だった彼女が湖に沈めた、母親の形見を入れた箱だった。
震える手で箱を受け取った彼女は、そっと胸に箱を抱いた。箱を取り戻した実感が強まるにつれ、彼女は肩を震わせ顔をくしゃくしゃにして泣き出した。
「良かった。やっぱりこの湖は最高だな、透明だったからすぐに見つかったよ」
言いながら、濡れた躰のまま脱ぎ捨てたTシャツを着た。
「ありがとう…、ありがとう……!」
ユウジのTシャツの裾を握って彼女は何度も礼を言った。
「中身は大丈夫かな」
浸水していなければいいが…とユウジは思った。
ユウジの言葉に、彼女は箱のロックを解除した。中には更に小さな箱が入っている。その箱を取りだした彼女は手で触って確かめると、
「濡れてない…」
と、いまだ整わない呼吸の中で鼻を啜りながら報告した。
浸水していないという事が分って、ユウジは心底安堵した。
「良かったな!」
彼女は頷いた。そして、その箱を開ける……。
肉親の形見となると、ずいぶんプライベートな部分になるので、軽々しく見てはいけないような気がして、ユウジは何となく視線を外した。
しかし、興奮した声で
「見て!」
彼女は可愛らしいリボンを何本も持っていた。
「リボン?」
「そう。ママがいつも私の髪につけてくれてたの。これ!これがママの一番のお気に入り!」
ふわふわと広がるスカーフのようなリボンを目の前に掲げながら、彼女は笑った。
彼女の初めての笑顔に、ユウジは釘付けになってしまった。可愛い。
ユウジから何の言葉も返って来ない事で、自分がはしゃいでいると気付いた少女は恥ずかしさのあまり慌てて俯いた。
うっとりと堪能していた笑顔が下を向いてしまって、今度はユウジがはっとした。ぼけっと見つめ続けていたのだ。焦って取り繕おうと口を開く。
「君の髪色に良く似合いそうだ」
取り繕うどころか本音が出ていた。ユウジは真っ赤になって黙った。
「……私は…マリュー。あなたは…?」
そう訊ねる彼女の顔も、ユウジに負けないくらい赤かった。
「……ユウジ…」
「ユウジ…」
「うん…」
彼女はハッとして、ポケットからハンカチを取り出し、ユウジのまだ滴の垂れる毛先にあてた。
「大丈夫だよ」
ユウジは恥ずかしそうに身を引いたが、マリューは上体を伸ばして距離を詰め、続けた。
一生懸命に髪の水滴をハンカチで吸い取っていたマリューだったが、ふと我に返り手が止まった。ユウジの顔が近い。ユウジの琥珀色の瞳に見つめられている。マリューもユウジを見つめた。不思議な力が作用して、二人とも視線が外せなくなってしまった。
「マリュー……」
無意識のうちに彼女の名前を呟いたユウジは、彼女の青い瞳に吸い寄せられるように顔を寄せた。
さっき青い湖水に潜ったように、青く澄んだ二つの水晶へユウジは引き込まれて行った。
仕事が終わってアレンが部屋に戻ると、ルームメイトのユウジが明りもつけずにベッドに腰かけていた。
「どうしたんだよ、こんな暗い中で」
廊下から差す照明にうっすら浮かび上がるユウジの顔が、眩しそうにアレンを見上げた。
「ああ、お疲れ、アレン」
自分と違って仕事だったアレンに労いの言葉を掛けたユウジの視線が、すぐにアレンの顔から何もない宙を彷徨う。
その様子から、わざと灯りを点けずにいるのかもしれないと感じたアレンは、部屋の照明は付けずに自分のデスクライトをつけた。労働の疲れからベッドにどさっと寝転がったアレンにユウジが話しかけた。
「今日さ、カグヤ達を町へ送ってった帰りに、すごいキレイな湖見つけてさ」
「へぇ、湖」
「ああ。あんまりキレイだから、車停めて水際まで降りてってみたんだよ。そしたらそこに…」
ユウジの言葉が途切れたので、アレンはむくりと頭を上げてユウジを見た。ユウジは俯いていたが、すぐに顔を上げてアレンを見返しながら続けた。
「女の子が泣いててさ」
「……女の子…?」
一瞬、何の事だか分らないほど、それはアレンの予想外の言葉だった。
「話しを聞いてみたらさ、その湖は死んじゃった母さんとの思い出の湖で、毎日来てるんだって。でも親父のせいで余所に預けられちまうらしくて、湖を見に来れなくなるから、それで悲しくって泣いてたんだってさ」
「へぇ……」
アレンは何故か自分の心臓がどきどきして来るのを感じながらユウジの顔を見つめていた。
「どう思う?」
「……え?」
「彼女は行きたくないんだぜ。泣くほどここを離れたくないってのに、可愛そうだよな」
アレンの心臓がドクンと跳ねた。
変だ。幼い妹のカグヤを「こんな小さいのに孤児になっちまって可愛そうだ」と言う時とは明らかに違う表情だし、口調も違う気がする。
「でも…親の言いつけじゃあ……、その子いくつなんだよ?」
「同じ十七。もう小さな子供じゃないんだし、大人の勝手な命令に従う義務はないだろ?」
確かに、自分達は五年前にはすでに孤児だったので、大人の命令も保護もない状況で生きていた。
「俺、彼女に言ったよ、ちゃんと親父に話せって。そしたら、もう何度もしたけど分ってくれないんだってさ。でも、そこで諦めたらおしまいじゃん? だから、今夜もう一度説得してみろって言ったんだ。で、結果報告を明日聞く約束したんだ」
一気に話し終わったユウジの目が、アレンのデスクライトの光の輪の外でうっすらと光っていた。
アレンは確信した。ユウジはその女の子に惚れたんだ。間違いない。
「……で? 結果聞いてどうすんの? 親父を説得できてなかったら…」
親友の初恋に気付いた動揺を押し殺しながらアレンは訊ねた。
「…それが分らないから、おまえに訊いたんじゃんか……」
さっきの勢いを急にしぼませて、ユウジは項垂れた。
「どんな子?」
予想外のアレンの言葉に、思わず顔を上げたユウジだったが、あっという間に頬を赤くしてまた俯いた。
ユウジの昂揚がアレンの動悸を強める。
「可愛い子?」
愚問だとすぐに気付いたアレンは、抑えていられなくなった。
「可愛くないわけないよな、おまえが惚れちゃうんだもんな!」
驚いたユウジは真っ赤な顔を上げて、目を丸くしてアレンを見ている。
「どんな子なんだよ、話せよユウジ」
ひとしきりアレンはユウジを尋問した。しどろもどろと答えるユウジを見ながら、アレンの胸にはいろいろな思いが湧いた。恋が成就するよう応援してやりたい。でもユウジが離れていくような寂しさも感じてしまう。女の子を好きになるってどんな気持ちなんだろう。その子とどうしたい、どうなりたいって思ってるんだろう。
想像を巡らせたアレンは、しかしこの恋はあっさり終わる事に気付いた。
「でもさ、ユウジ。どうにもできねーよ。その子は湖と離れたくないんだろ?
家出する覚悟でもありゃ、ザナックに頼むって道もあるけど、それじゃここから離れるってのは変わんねぇもんな。それは嫌なんだろ、その子」
ユウジはがっくりと項垂れて両手で頭を抱えた。
「……そうなんだよなぁ……」
しばらく沈黙が続いた後、大きく溜息を付きながら漏らしたユウジの言葉にアレンは耳を疑った。
「俺がここに残るなんて無理だしなぁ……」
「え…?」
―――ここに残るという事は、すなわち船を降りるという事か。
ユウジは船を降りる事を一瞬でも考えたのだ。いや、一瞬ではない、今も決めかねているのだ。
「バカな事言うなよ、おまえ…、」
起き上がったアレンは身を乗り出したが、言葉が続かない。
そんな事、今まで一度だって考えた事はなかった。
一流の船乗りになって、ザナックから独立して、自分達の船を持つ。
それが五年前からの二人の目標だったのだ。この目標があったからこそ、日々の厳しさにも耐えて来られた。同じ目標に向かって一緒に進む親友が横にいたから、亡くした肉親を思って寂しさを募らせた夜でも泣かずに眠る事が出来た。
今のアレンの人生設計の、どのシーンにもユウジは必ずいるのに。
ユウジは違ったのか。
「おまえが船を降りる……?」
「分ってるよ、俺がここに残った所で何の役にも立たない。湖からそんなに離れない距離をコロニーの中で家出したってすぐに見つかっちまうしな。…くっそ、何か、何かないかな…」
「何もねぇよ!」
すでに船を降りた上での作戦を考え続けているユウジに、思わずアレンは言い放ったが、その激しい口調に驚いて顔を上げたユウジにさらに腹が立った。
俺がこんなにショックを受けている事なんて、少しも気づいていない。分ってない。
「おまえが船を降りるなんて、俺は絶対、絶対に認めないからな……!」
「アレン…!」
はっとした顔をするユウジを残してアレンは部屋を出て行き、そのまま朝まで戻らなかった。
翌朝ザナックからの艦内放送が流れた。
商談は成立し、今夜遅くの出航が決まった連絡だった。
アレンは慌ててユウジを探し走り回った。出航が決まった船をすぐに降りてしまうのではないかと恐怖に駆られたのだ。
しかしユウジは持ち場で普段通りに仕事に就いていた。一晩戻らなかったくせに息を切らせて現れたアレンに、ユウジはバツが悪そうに笑いかけた。戻らなかったのも駆けつけたのも、自分のせいだと分っていたからだ。
どう切り出せばいいのか見当がつかないアレンは、しばらく息を整えるだけで何も話せなかった。
「アレン、ごめん」
先にユウジが切り出した。どちらの意味での謝罪の言葉なのかわからず、鎮まりかけた息をアレンは?んだ。
「昨日あんなこと言って…。船は降りないよ、俺」
一番欲しかった言葉がするりと本人の口から出て、アレンは飛び上がらんばかりだった。
「ああ、うん、そうか」
「おまえの言うとおりだもんな。今の俺じゃ何もできない。だから俺、一日も早く一人前になる。マリューがあの湖の傍で暮らすのを、誰にも邪魔させない力を付けるって決めた。ありがとなアレン、一晩じっくり考える事が出来た。俺、ガキだったよ」
ユウジは笑った。
その笑顔を、初めて見る顔だとアレンは思った。昨日までのユウジとは違う。取り残されたような気分に襲われたアレンにユウジは続けた。
「今日、午後、ちょっと俺、脱け出すからさ」
「会いに行くのか」
「うん。会って、やっぱ親父さんを説得できてなかったら、いつか必ず連れ戻してやるから、とりあえず預けられる先で頑張れって言って来る。預けられる先も聞いとかないと迎えに行けないし。でさ、おまえも一緒に行かないか?」
「え?」
「マリューに会わせたいんだよ、おまえをさ。それに湖、見せたいし。すっげー綺麗だからさ」
「…わかった、行くよ」
「なんだよノリが悪いな、『マジで? 行く行く!』って言ってくれよ」
ユウジはまた笑った。アレンには眩しかった。
首尾良く揃って抜け出した二人は、湖のほとりで車を停めた。
湖は昨日と同じく、人工陽光を反射させてキラキラと碧く輝いていた。
確かに綺麗だ。そう思うも、ユウジを骨抜きにした女が気になって、アレンは湖を眺めたりできなかった。
ユウジは今一度腕時計を確認すると、昨日と同じ経路で木立の中を歩いて行った。その背をアレンも追う。
水音がはっきりと聞き取れる頃、木立は終わって水際へ出た。
そこに人影はなかった。ユウジは彼女がうずくまっていた辺りをじっと見つめた。
「ここで会ったんだ?」
「ん…」
木立の陰から現れるはずの少女を見つけるために、アレンは背後を振り向いた。
木々の間に視線を泳がせていると、低い小枝で何かがひらひらとしているのに気が付いた。正体は分からないが明らかに人工物だ。
アレンが一点を見たまま止まっているのに気付いたユウジは、その視線の先を追いかけた。
「あ…!」
ユウジには見覚えがあった。
木に駆け寄り手に取ると、間違いなくそれは、昨日彼女が夢中になって見せてくれたリボンだった。しかも、母親が一番気に入っていたという、ふわふわとした幅広の物だ。
「何?」
傍らに立ってアレンは訊ねた。
「彼女のだ」
「え…? 本当に?」
答えるより先に、リボンの端に文字が書かれているのに二人とも気が付いた。
―――ユウジの幸せを祈ります。ありがとう。さようなら。
ユウジはしばらく動かなかった。アレンはユウジの肩に一度手を置くと、そっと離れた。
マリューは消えてしまった。
ユウジの決意も知る事無く、ここを離れるに違いない。
彼女の家も、フルネームも聞いていない。数時間後には出航だ。もはや探し出すのは不可能だ。
もしかしたら、もう一度だけここへ来るかもしれない、という希望を捨て切れないユウジに付き合って、アレンは離れた場所に腰を下し湖を眺め続けた。アレンの目の前で湖面は碧から橙へと色を変えて行った。
いよいよ持ち場の先輩から帰艦命令の怒りの電話が来たので、アレンはユウジを促して湖を後にした。
ユウジの意気消沈ぶりは強く、一人だったら船に帰って来れなかったのではないかと思うアレンは、一緒に来ていて良かったとつくづく思いながら車を走らせた。
帰艦した二人は先輩から拳骨を一発ずつ貰い、機関部クルーの出航前ミーティングの輪の外側に並んだ。チーフは腕時計を確認すると、エンジンの動力音に負けないよう声を張り上げた。
「乗船した依頼主も落ち着いたって事で、予定通りの出航サインが出た。ちょうど二時間後だ。というわけで、出航前再確認するぞ。依頼主、ミスター・ベキーチャ。依頼内容、ミスター・ベキーチャの娘、ミス・マリュー・ベキーチャの極秘移送」
精神的疲労感を感じながらただ聞いていたユウジとアレンだったが、マリューという名前を聞いた瞬間、チーフの顔を凝視した。
「移送先はM727。行程は往復3週間。今回、護衛ではなく移送という注文だったのは、対海賊襲撃。何故海賊に狙われるのかは、まあ、金持ちだし、まあ、そーゆーことだ」
チーフの失笑につられて、輪からも笑いと共に私語が漏れる。
「金持ちってのはろくでもねー奴ばっかだかんなぁ」
「ろくでもねーコトしてっから金持ちなんだよな」
「おいおい、そのおこぼれで俺らの仕事があるんだからよ、悪口はいけねーや」
男たちの会話の中、アレンは固まっているユウジに囁いた。
「ユウジ…、マリューって……」
「分らない……、でも…」
ユウジの混乱ぶりは痛いほど分る。暗黒の闇に光が一筋射し込んだのだ。
「約束してた時間って、もう乗艦準備だったから来れなかったんじゃないのか? おまえも自分のコト船乗りだとか、船の名前とか、何も話してなかったんだろ? 彼女、時間切れでどうしようもなくて、せめてリボンだけ残して行ったんじゃないか?」
もちろんユウジ本人も同じ仮説を立てていた。アレンにも言われてますますそれは確信に近づいて行く。
「……彼女かどうか確かめる…!」
深刻な顔で決意するユウジの肩を、アレンは満面笑みを浮かべて叩いた。
「なあ! もし彼女なら、これで行き先が分って良かったじゃないか! 迎えに行けるぜ!」
ユウジはポケットの中でリボンを握りしめた。
そうだ、ただ時間切れで会えなかっただけで、会いたくなかった訳ではないのかもしれない。一番大切にしていたはずのリボンを俺に残してくれたのだから…!
「ゲストルームに行く口実、考えないと……」
「親父もいるぜ、きっと」
「だよな、……」
どさくさに紛れて強行突破したいが、ザナックに迷惑をかけてしまうのはダメだ。
逸る気持ちを必死に抑え、興奮して声が大きくならないように気を付けながら喋っている二人の側で、男達の会話も続いていた。
「影武者船まで飛ばすってのは本当なのかよ?」
「もうとっくに出航したらしいぜ」
「すげえ念の入れようじゃねぇか。なんでそんなに狙われてんだ?」
「娘を誘拐できりゃ、身代金がっぽりだからじゃねーの?」
そりゃあ違いねぇ、と沸く。
「その娘ってのを、嫁にくれに行くんだろ?」
「マーズの大富豪はジジイだぜ」
「見内になれりゃぁいいんだろうよ、やっぱろくでもねえ野郎だぜ」
「実の娘なんだろ?」
「まだ若いって聞いたぜ」
「金持ちってのはいいなぁ、若い嫁さん貰えてよ」
笑い合う男達の背を、ユウジはじっと見ていた。アレンも同じだった。
このコロニーを離れるのは、結婚のため?
ユウジの頭の中で、マリューと結婚が結びつかない。だってマリューはあんなに可愛くてまだ十七歳だ。それがジジイと呼ばれる年齢の男と結婚なんて何の冗談だ。
チーフの解散号令も耳に入らず、ユウジは立ち尽くしていた。傍らでアレンは自分に言うともなく呟いた。
「……別人かもしれないし」
「…………」
すぐに先輩から怒声が飛んで来たので、アレンはユウジの腕を掴んでその場から引き剥がし、持ち場へ戻った。
後篇に続く
3/28更新予定
|
|