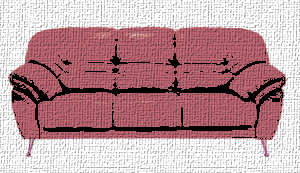 |
||
| <<TOP <<BACK NEXT>> | ||
| 第23話 First experience | ||
| 「だめ、ジョー。来ないで」 ジョーを見上げてリリが言った。横たわる彼女の傍らに立ち、彼女を見下ろしながらジョーは言った。 「うるせー」 彼女のからだを覆っている毛布を鷲掴みにして、ぐいと引っ張った。 「あっ、いや!」 引き剥がされまいと、彼女も必死に手繰り寄せる。 「放せ!」 「いやよ!」 毛布を引っ張り合うが、とうとう毛布ごとリリを引き寄せたジョーは、荒い息遣いの中、吐き出した。 「好きなんだって気づいちまったって言ってんだろ! なんでわかんねーんだよ!」 「だって、」 「だってじゃねぇ! おまえが何て言おうがオレのモンなんだからな! オレは寝る! 大好きなこのオレのソファでな!」 どけ!とリリを放り出すと、ジョーはソファに飛び込んだ。 ラグの上に転がされたリリは、もがきながら起き上がると叫んだ。 「 私だってこのソファで寝るのが大好きなんだから!」 「オレは家主だ!」 「そんなの関係ないもん! ソファは私! ジョーはベッド!」 ジョーが自分にしたように、ぐいぐいと毛布を引っ張った。 「引っ張んなよ!」 「きゃっ!」 ジョーが思い切り毛布を取り返すと、リリまで一緒に小さな悲鳴を上げながらジョーの上へ飛び乗って来た。頬に彼女のおでこがごんっとぶつかる。 「いって……!」 目の前にリリの顔があった。ジョーは突然のその近さにぎょっとしたが、しかしリリは電光石火の早業でソファの背とジョーの間に自分をねじ込み始めた。 「てめ、このクソボーズ、何しやがんだ」 しかし、文句を言うものの、ジョーはどうにもできなかった。どうしたって体のあちこちが当たりまくって、骨だったり肉だったり、固かったり柔らかかったり、この状態は何だかやばい気がして来たからだ。 ジョーが動けないのをいいことに、とうとうリリは無理矢理ぎゅうぎゅうに並んで横たわった。ジョーの胸に突如湧いた不本意な緊張など露程も知らないリリは、これでジョーを突き落してしまえばと、不敵な笑みを浮かべて目の前のジョーを見た。二人の間は、ほんの数センチしか空いていない。これはジョーにとって無条件にキスの距離だ。 リリがジョーを突き落そうとした瞬間、彼は自らソファから下りて立ち上がった。 「ガキじゃあるまいし、バッカじゃねーの?」 心底、呆れた風を装ってソファから離れ、テラスの扉を開けた。涼しい秋の夜風が流れ込んで、ジョーの頬を冷やして行く。 そんな彼の背に、リリは言った。 「ガキでもバカでもいいもんね。じゃ、私がソファってことで。おやすみなさい」 (まったく、人の気も知らないで……!) 一呼吸、深く冷気を吸い込んで、ジョーは振り向いた。 「勝手に決めてんじゃねえよ。勝負しろよ」 ジョーは拳を突き出した。 じゃんけんに負けたジョーは、寝室のベッドの中で数えていた。 オーラーデ島でのバカンスの全五夜、帰宅した夜、セヴァ・ファームでの七夜、ファームから帰宅した昨夜。実に二週間ぶりの自分のベッドだ。 ――それにしても… と、ジョーは眉間に皺を寄せて考える。このベッドにリリを寝かせていたのはたったの二夜だ。だのに、明らかにリリだろうと思われる香りがする。風呂で使っている物は同じ物なのに、いったいこの香りはどうやって発せられるのか? 謎を解こうとしたジョーは、うっかりここへ横たわる彼女を想像してしまった。 最初の夜、酒を垂らしたスープで眠らせた彼女を、ブランケットごと抱き上げてここへ運んだ。彼女の重みを腕は覚えている。 ベッドに下した後、見下ろした寝顔は、アレンへの涙がまつ毛についたままだった。 でも昨夜は、セヴァ・ファームでの疲れが一気に出て、酒の細工などせずとも、風呂から出た彼女はリビングのローテーブルに突っ伏した状態で撃沈した。肩を揺すっても何をしても起きなかったので、やはりジョーがベッドへ運んだのだったが、一週間前とは違って、彼女のまつ毛に涙は光っていなかったし、顔色もすこぶる良かった。むしろ風呂上りで頬などはうっすらと紅く色付いていたし、そうだ、頬だけじゃない、唇もぷるんと紅く……。 脈拍が一気に上がったジョーは、記憶のスクリーンを強制遮断した。がばっと起き上がり、荒々しい勢いで着替え始める。 (これは絶対に欲求不満だ。オレ、いつから遊んでねえ? 今年はオーラーデでも遊ばなかった、そうだ、こんなことは初めてだ!軽く二週間、こんなに遊んでねえのも初めてだ…。ありえねえ! おかしくもなるわけだぜ!) “おかしくなる”とは、リリでドキドキしてしまったことだ。今のジョーには、違う理由が必要らしい。 あっという間に外へ出たジョーは、地上から遥か頭上の自分の部屋を見上げた。真っ暗である。ソファを巡ってジョーとバトルをしていたくせに、ものの15分でリリは熟睡していた。 ――夕飯に飲んだワインのせいだよな。たった一杯で真っ赤だったもんな。 美味しいと言っていた。酔ったらしく訳もなく「えへへ」と笑ったりしていた。嬉しそうだった。多分、気がかりだったアレンの事が一安心できたからだろう。そしてきっと笑い上戸なんだ。 その彼女を一人残して来た部屋を仰いだ。不安が過る。 ――もし目を覚まして、オレが居ないことに気付いたら不安になるんじゃないか? せめて書き置きをして来るべきだったか?……いや、大丈夫、朝までには帰るし……。 と、ふと気づく。 ――……いやいや、そもそもなんでアイツに遠慮してんだよ? そこ、おかしーだろオレ! 町中へ向かって歩き出した。だが、足並みはすぐに速度を落とし、一つ目の角も曲がれずに立ち止まってしまった。 「………しょーがねーなぁ……」 舌打ちをして、ジョーは引き返した。 薄暗いリビングへそっと入ると、何も変わった様子はなく、リリはぐっすり眠っていた。改めて傍らに立ち見下ろす。彼女はまるでそれがベッドであるかのように、どこもはみ出ることなく収まっていた。 (ジャストフィット? ……チビ) ジョーは笑いをかみ殺した。リリは軽い寝息を立てて気持ち良さそうに眠っている。 ジョーは先程ベッドで悩まされた謎を思い出し、その不思議な香りを確かめようと、彼女の顔のそばへ屈みこんだ。さすがにちょっと変態っぽいとは思ったが、誰が見ているわけでもない、彼女の周りの空気を吸ってみようとした。その時、 「仕方ない、じゃぁ、一緒に寝ましょう」 突然リリが言った。文字通り、ジョーは心臓が口から飛び出そうになり、さりとて微塵も動けずそのままの姿勢で固まった。 ――起きてたのか? ――ばれた? ――つか、一緒に寝るって何だ? ――…一緒に寝たいのか? ――「仕方ない」って、まるでオレが強請ってるような、それにおまえが渋々応えるような、なんでそんな立ち位置なんだ? ――つか、おまえはどうなんだ、おまえがそうしたいんじゃないのかよ? 石像のような影の中、ジョーの脳内は大暴走する。 「……おまえ、」 ジョーが言いかけた時、 「おいで、パメラ……」 とリリは言うと、寝返りを打ってわずかに横向きになった。硬直の解けたジョーは心の中で吠えた。 (器用に標準語で寝言言うんじゃねーよ!) 名前を呼ばれて、ジョーは覚醒して行った。うまく開かない目を片方だけわずかに開くと、リリの顔が覗き込んでいた。 「ジョーったら! どうして私がベッドにいたのよ!」 猛烈に怒っている。 「……うるせ〜なぁ、知らねーよ…」 面倒くさいのでとぼけることにした。 「知らないわけないでしょ!」 怒りの勢いでリリは毛布を引っ張った。 「バカ! 返せ!」 寝起きの男から掛物を剥ぐとは、なんて考えなしの女なんだ! ジョーは力任せに奪い返した。 手から毛布が離れた反動で、哀れなリリは思い切り尻餅を付き、さらにそのまま後方でんぐり返りまでしてしまい、昨日買って来た水色のパジャマの上衣がベロンとめくれて白い背中を披露してしまった。 「あ…!」 吹っ飛んで行くリリを慌てて目で追っていたジョーは、くるりと転がった白い背中と一緒に、一瞬だけ白い胸…らしき曲線も見てしまった。 でんぐり返りからがばっと起き直ったリリは、パジャマの裾をぐいぐいと下げたものの、座ったきりしばらく立ち上がれないでいた。 髪をぼさぼさにし、真っ赤な顔でうつむいたまま、パジャマ姿でぺたんと座っているリリが…、ジョーの鼓動を乱打する。全身が心臓になりそうだ。 「ま、まだオレは寝るんだよ…!」 ソファの上で必死に寝返って、彼女に背を向けた。 リリが立ち上がり、どすどすと歩く気配がした。キッチンへ向かったようだ。カチャカチャと音がする。 コーヒーを淹れるんだな、と思いながら、ジョーは右脳を静めて左脳をフル回転させるべく、めちゃくちゃに計算を始めた。目を閉じてひたすらに数字を並べて足して引いて掛けて割る。程なくコーヒーの香りが漂って来た。しかし計算に没頭。 「ふんだ。ずっと寝てればっ。コーヒーだって冷めちゃうんだから」 一向に起きないジョーのカップをローテーブルに置いて、リリはテラスへ出て行ってしまった。 それでもジョーは、しばらく計算をやめることができなかった。 家政婦リリは、黙々と働いた。洗濯は機械がすべてやってくれるので、掃除に取り掛かったが、ジョーの部屋はとてもシンプルで物も少なく、あっという間に終わってしまう。料理はスカスカの食品棚に僅かにストックされていたレトルト食品があるので、とりあえずそれらを先に消費して行く事にしているので、これまた手間がかからなかった。 ゆっくりと起床してからの午前中いっぱい、ジョーは書斎に籠っていたが、部屋を出てリビングやキッチンにいるリリを見るたびに、妙な気分に襲われて、そそくさと書斎に戻る、という具合だった。 この妙な気分は、欲求不満のせいだと信じて疑わないジョーは、午後になったらパーズンへ寄って、そのまま遊びに行こうと計画した。連休も今日で終わりだ。心残りの無いように過ごさなければ。あんなボーズで変な気になっちまうなんて、よっぽど遊び足りてないに違いない。 あくまでもそう思い込もうとしているジョーだったが、自分の部屋にいる彼女を見るだけで、胸はどきりと跳ね上がり、脈はとくとくと駆け足になって、彼女がこちらに気付くまで、目を逸らすことができずに見続けてしまっていた。 (ここに他人がいるなんて初めてだからな。そりゃ慣れてないから焦るよな) ジョーはそう解釈した。 ジョーが外出着に着替えてリビングに来ると、リリはすでに昼食を片付け終えていて、テラスのベンチに膝を抱えてぽつりと座っていた。結局あれから気まずいままで、今だにまともに口をきいていない。 控えめな秋風が彼女の金糸の髪を揺らしている。テラスへ身を乗り出してリリの背後から声をかけた。 「ちょっと、パーズン行って来る。明日っから店開けるから、ちょっとその準備に…おまえは自由にしてていい、から、……」 何故、語尾が消えそうになるのか自分でもわからない。リリが顔を上げた。 「帰りは?」 「え?」 「何時頃になるんですか?」 ジョーはぎくりとした。 (帰りって、……、そりゃ、真夜中だぜ、つか、そっちがメインなんだから。……もしかして何か勘付いたのか?) ジョーが考え過ぎた瞬間、 「夕御飯、何時に用意しておいたらいいんですか?」 彼女は、夕飯の都合を気にしていたのだった。 誠実な家政婦たらんと一生懸命のリリ。言葉遣いも仕事モードなのか。いや、これは多分、嫌味のつもりなのだろう。彼女を見下ろしたまま返事のできないジョーに、彼女は失望したのか悲しげに(ジョーにはそう見えた)目を伏せた。 「おまえも行こうぜ」 言葉が口から飛び出していた。頭を通らずに、脳の指示も無しに、リリに同情してしまった胸からストレートに口へ指令が行ってしまったようだ。 (ななななな、何を言ってるんだ、オレは? 遊びに行けなくなるじゃねーか!) 内心大慌てのジョーだったが、 「うん!」 リリが満面の笑みで立ち上がったので、つられて笑い返しそうになったのを無意識のうちに押し殺し、かろうじて仏頂面を装いながらも、 「バイクだぞ、上着持って来い」 と、また脳をショートカットして喋っていた。 エレベーターに、ジョーの黒いバイクと共に乗り込んだリリは訊ねた。 「車じゃないんだ?」 「バーカ、オレ様はライダーだぜ?」 「セヴァさんとこは車で行ったじゃない」 「荷物とおまえの両方、バイクに積めねーだろ?」 「“積む”って……、ひどい」 あっという間に地上一階に到着した。ぐい、とバイクを押してエントランスを歩いて行くジョーにリリも続く。敷地の外に出ると、 ジョーはバイクに跨り、両足を下してバイクをがっちり固定した。 「おら、乗れ」 とリリを促す。アレンの後ろに乗っていたのだから、今更乗り方の手解きも要らないだろう。 しかしリリはもたもたしている。 「どうした?」 「えと、ないよ、足乗っけるとこ…」 「あー、悪りぃ、出してなかった」 彼女に言われてジョーは気付いた。このバイクのタンデムステップを出すのが今日が初めてだという事に。このバイクで二人乗りはした事がないという事だ。 「あの、つかまっていい?」 「チビだから、よじ登るの大変だよな」 「ちょっとつかまるだけよ!」 ジョーの肩に手を置いて、リリはよいしょっと言いながらタンデムシートに乗り上がった。 揺れるバイク、肩に乗る僅かな重さ。今まで感じた事のない感覚だ。二人乗りはした事があるのに、何なんだ? ――女乗っけるの、初めてなんだ…! 「乗ったよ」 背中でリリが言った。 ――女のタンデム初体験がこいつかよ……。 頭の中で面白くなさそうなポーズを取る。 「手、出せ」 遠慮がちに伸びて来た手を、自分の腹の前で重ねた。その小さな手を見下ろして、誰も見ていないのをいいことに、まんざらでもない表情を浮かべたジョーは、行くぞと声をかけ、エンジンをスタートさせた。 モニタの中で、ミネルバは脱力した。 「あの直後に、そんな激変するなんて〜〜〜…」 「あの直後に、そんな出張に行くなんて〜〜〜〜」 ミネルバの口真似をしてジョーが返した。 「仕方ないでしょ、仕事ですもの!」 今しがたサラに連絡をしたところ、アレンから電話があった事、さらには出張直後にジョーからも電話が入っていた事を教えられ、(すでに一週間以上経過している。ミネルバは夫の呑気さに一瞬眩暈がした)慌てて電話をして来たミネルバだった。 「おっかねー。まぁ、そーゆーわけだよ」 「本当だったのね、アレンの話…」 ミネルバは、ジョーより先にアレンに連絡をして、事の顛末を聞いていた。 アレンとジョーの二人から連絡が入っていたと聞いて、アルテミスの事だろうと直感した。オーラーデ島の浜辺で打ち明けられたアレンの抱えている苦悩。引き上げる朝に見てしまったジョーとアルテミスのやり取り。三人の間で、何かが崩れて生まれるような漠然とした予感がミネルバにはあったのだ。 ついさっき話したアレンは、拍子抜けするくらい穏やかだった。 ――本人が「アルテミスじゃ嫌だ」って言うんじゃ、どうしようもなくてさ。もう認めてやるしかなかったんだよ。 俺も俺でさ、アルテミスじゃないけど愛してくれって言われたら、応えらんなくて。 アルテミスじゃない人生で幸せになれるように見守るしかないって……。まぁ、そんな感じなんだ―― あれが、アレンから彼女への、身を切るような精一杯の愛情なのだと、ミネルバには痛いほど分った。 「大事に受け取ってね、アレンの気持ち」 「あ? オレじゃなくてアイツに言えよ」 「あなたもなの、ジョー」 ミネルバはモニタの中からジョーをじっと見て、静かに言った。 (私は知ってるんだから、あなたの本心。あなた自身も気づいていないらしい本心を…! 精神科医をなめんなよ?) 色々と言いたい事をぐっと飲み込んで、 「まあ、とにかく、仕事の事は安心して待っててって彼女に伝えておいてね」 「あー、代わろうか?」 「え?」 家にかけても携帯電話にかけても捕まらなかったジョーを、ダメ元でバイクショップにかけてみてようやく捕まえていたので、てっきり一人だと思っていたミネルバは驚いた。まさかアルテミスも連れて来ているとは。まるでデートのようじゃない? 他人事ながらドキドキしていると、モニタの中でジョーが奥へ向かって「ボーズー」と呼んだ。すると、怒っているような声が聞こえて来て、立ち上がったジョーの陰からアルテミスが姿を現した。 「ミネルバさん!」 ジョーがミネルバと話しているとは知らなかった彼女は破顔した。 「ああ、ごめんなさいね、いつでもどうぞなんて言っておきながら留守にしちゃって! でも良かった、元気そうで…!」 「はい、ジョーに……」 はっとして、きょろきょろとあたりを伺い、ジョーが奥のピットでバイクをいじっているらしい音を確認すると、 「ジョーにとっても助けられて」 と打ち明けた。本当に心から感謝しているようだ。 「家政婦させられてるんですって?」 「はい、でもそれはジョーが気を遣ってくれたんだと思います、私が居やすいようにって」 ああ、良く分ってるのね。とミネルバは嬉しかった。密かに彼女を気遣う彼、気遣われている事に気付いて密かに感謝する彼女。 「帰ったら、仕事の相談しましょうね」 「はい、ありがとうございます。ミネルバさん、私、一生懸命働きますから、よろしくお願いします!」 「こちらこそ」 ミネルバは、アルテミスの前向きなパワーを頼もしく思った。 「あのミネルバさん、私、名前なんですけど…自分でつけた名前があるんです……」 「あら。大丈夫よ、私が保証人になるから、その名前で通せるわよ。 なんて言うの? あなたの名前」 「リリです!」 「まあ、可愛い!」 「ありがとうございます…」 彼女は恥ずかしそうに微笑んだ。モニタの奥にジョーの姿を見つけたミネルバは、彼に向かって言った。 「ねえ、ジョー、可愛い名前ね、リリ」 「あ? 鈴虫みてーじゃん」 この一言はリリには衝撃だった。 「! だから全然呼んでくれないの?」 「おまえなんかボーズで十分だっつーの」 そんな理由なんかでは納得できないし、ショックも消えない。とても気に入っている名前を、虫呼ばわりされたのだ、しかも……ジョーに。 「ジョーはね、その名前があんまりあなたにぴったりで可愛いから、照れちゃってるのよ。ふふふ、ジョーったら天邪鬼よねぇ」 天邪鬼。リリはセヴァの言葉を思い出した。 “ジョーは天邪鬼なんだよ。アイツの憎らしい言葉は全部逆に取ってごらん。案外それが本音だよ。” なるほど……。なら、鈴虫みたいだとは思っていないし、ボーズで十分なんてのも嘘よね? リリが考えを巡らせた僅かな隙に、 「ミネルバ、働き過ぎ、頭イカレてんぜ。じゃあな!」 と、ジョーは電話を切ってしまった。 「あ、ちょっと、ひっどーい!」 「うっせーよ、クソボーズ」 ボーズにちっとも嬉しくない形容詞まで付けられて、 「頭きた! 私のメットはこれにするから!」 そう言うと、リリはヘルメットをがばっと被った。 「あ!」 ジョーは腰を浮かせた。そのメットは、彼女が初めてここへ来た時に被っていた、昨年のグランレースのプレミアムメットだ。 「おまえ、それ、外せなかっただろーが……」 呆れ顔のジョーに、リリは得意げに言い返した。 「ふんだ。ちゃんと覚えてるわよ。ここをぽちっと」 ぽちっとボタンを押すと、顎のバンドがしゅるっと縮んで首に食い込んだ。咳込む。 「……前回もソレで締めたんだろーが……」 「わ、わざとよ、やあね。分ってるわよ、これでしょ?」 今度はシールドに色味が加わった。あら?と言いながら指が触れるボタンを次々に押して行く。 彼女の手を掴んだジョーは、ポンとベルトを解除して、冷ややかな目でリリを見下ろした。 「何をちゃんと覚えてるって?」 リリは、おずおずとメットを外すと、 「覚えてるってば。“ありがと”でしょ?」 にっこり…というか、えへへと頬笑んだ。不意打ちに心臓が跳ね上がったが、かろうじて無表情を死守したジョーは、彼女の手からメットを取り上げると、 「もうコイツで遊ぶな」 と言ってカウンターの台座に戻した。そのまま壁から一つ、小さなメットを外すとリリへ渡した。 「おまえのはこれ」 半キャップタイプでゴーグルが付いている。 「…ありがとう、ございます…お借りします…」 「ちゃんと目ン玉おろして」 ジョーはゴーグルをリリの目に合わせた。 「ねえ、どうしてジョーはメット被らないの?」 「レースでもないのに、必要ねえじゃん。ま、オレも、もう少し寒くなったら被るけどな。暖けーんだぞ、メット」 そう答えながら、メットの上からこつんと小突いた。 バイクに跨り、エンジンを掛ける。秋晴れの空に重低音が響く。 失礼しますと言って、リリがジョーの腕に触れて来た。よいしょと言いながらバイクの後部座席に上がる。 ふと、リリが初めてパーズンに来た日を思い出した。 ――まさにこの場所で、アレンのバイクに乗ったこいつを見送ったんだっけな。 ちくりと胸が痛んだが、両脇からおずおずと伸びて来た小さな手に、我に返った。 「ちゃんと繋げよ」 「うん」 手が腹の前で重なったのを見届けて、ジョーはローギヤを入れた。 「どこに行くの?」 「天国」 「え?」 ドルルルル…と地を這うような音を吐き出してバイクは走り出した。 |
||
| 第23話 First experience END |
||
| <<TOP <<BACK NEXT>> |  ぺた ぺた |
|
 |
||