 |
| <<TOP <<BACK NEXT>> |
 |
| <<TOP <<BACK NEXT>> |
| 第20話 星に願いを | ||
| パメラがセヴァ・ファームへ引き取られたのは、三ヶ月ほど前だった。 ファームのあるビドル島よりさらに西へ海を渡った島に住んでいたパメラは、父親の運転する車に家族で乗っていて交通事故に合った。隣に座っていた三つ年上の姉は即死、身動きの取れない潰れた車内で、救出も間に合わず父親、母親の順に息絶えた。そうして四歳になったばかりのパメラは親類がいなかったため天涯孤独になってしまった。引き取り手がいない上に、事故で深く心が傷ついた彼女は、事故後もずっと病院の小児科病棟に預けられていた。 たまたま仕事の用事で島へ来たセヴァは、その病院の医師でもある友人からパメラの話を聞いた。彼女を訪ねて病院に行ったセヴァは、俯いたままのパメラとほんの半日ほど一緒に過ごすと、病院を出た足で役所へ向かい里親になる手続きをした。 その翌朝、事故から半年も過ぎた初夏、パメラは太陽が反射して眩しい海をセヴァと渡り、二十三人目の子供としてファームへ来たのだった。 「半年だぜ? あんなチビがよ、たった一人で保育ロボに見張られてよ。そりゃ、無口な引き篭もりチャンにもなっちゃうだろ?」 「……そうだったんだ」 「だから、おまえさ、パメラのこと、ちゃんと見てろよ。ロボじゃない、生身の根性みせてやれよ」 「…うん」 「しっかしなぁ。春に来た時、さすがにもう増やせねぇっつっててよ、その直後だぜ。セヴァ、どんだけガキが好きなんだか、呆れるぜ」 (あら、それはジョーだって……) 朝の厨房でキャベツを刻みながらジョーの話を聞いていたアルテミスは、一瞬手が止まった。だが、すぐにまた動き出す包丁は、初日だった昨日の朝よりスピーディだ。急ぐ度合いを心得たらしい。 アレンとの一件から立ち直ったわけでは無論ないが、三日前の夜の彼女よりは断然マシだ。予想通り、ファームの多忙さが効果絶大なのだと、ジョーは密かに大満足していた。 その日の昼下がり。メリンダは焼き上げたマフィンを包みながら、 「この子達と一緒に、畑へ行って来てみたら?」 と、アルテミスへ提案した。おやつ届け隊の子供たちが大喜びしたので、そのままアルテミスも出かける事になった。 セヴァ手作り台車に、お茶、コーヒー、ミルクのポット、コップ、そしてマフィンの籠を載せて、おやつ届け隊は畑道を進んだ。太陽はかなり傾いてはいるが、まだまだ明るく輝いている。 一つの丘を上りきると、突然目の前に鮮やかな色彩が広がった。赤や紫、黄色にピンクの帯が延々と向こうの丘まで伸びている。まるで大地に描かれた印象派の絵画のようだ。 その光景に圧倒されたアルテミスは足が止まってしまった。 「お姉さん?」 一人の少女に呼ばれて我に返ったアルテミスは、 「凄いねぇ…!」 と、思わず漏らした。見慣れている子供たちは取り立てて何の反応も無く、花畑の隣の畝で作業している仲間に大声で叫んだ。 「おやつだよー!」 アルテミスが慌ててそちらを向くと、歓声を上げて農具を放り出した子供たちが駆けて来るのが見えた。 その子供たちの後ろで、トラクターから降りた人影がこちらを向いた。ジョーだ。太陽を背にして浮かんだシルエットは、こんな場所で見ているせいなのかやたらと逞しく見える。いつものチャラチャラしたジョーと同一人物とは思えない。 (でも…あんなに重たいバイクを扱ってるんだもの…力はあるはずだから、) はずだから、逞しくても当たり前なのだ。と、訳も無く自分を納得させていると、ジョーの横にセヴァが現れて、 ジョーの背をばんと叩きながらこちらに手を振った。 自分の胸の高鳴りを抑えようと必死になっていたアルテミスは、セヴァにつられて手を振り返していた。 「あ、手振ってる」 可愛いねえ!と言いながらジョーの背をもう一度叩いて、セヴァは歩き出した。歩きながら子供たちに、手を洗えと叫ぶ。子供達は、畑の中に引かれている蛇口をひねって、じゃばじゃばと手を洗っては走り抜けて行く。手洗い場に最後に到着したジョーは、もたもたしている子供に、蛇口を指で押さえて水しぶきを浴びせかけたりして遊びながら、ほこりと汗にまみれた腕と顔をざぶざぶと洗った。そんな様子をじっと見ていたアルテミスだったが、到着した子供たちにおやつやミルクを手渡す作業で、てんてこ舞いになった。蜂の巣を突ついたような大騒ぎを何とか捌いて、子供たちが思い思いの場所に落ち着き出した頃、頭の上から声がした。 「ご苦労さん、オネーサン」 驚いて顔を上げると、いつの間にかすぐ横にジョーが立っていて、籠の中を覗き込んでいる。ついさっきジョーに見とれていた事は頭の片隅に素早く隠して、アルテミスは花の絨毯について訊ねた。 「ジョーこそご苦労様、ね、すごいね、花畑」 花畑はアルテミスの心を動かしたらしいと判断したジョーは、にやけそうになるのを押し殺して返事をした。 「そか?」 「何て花達なの?」 「あ? ああ、手前の紫色のがビクトリアブルーで、その隣の赤はスプレンデス…あー、どっちもサルビアって花の仲間。で、ちょっと細めのピンクのところはクレオメ、オレンジ色と黄色のがマリーゴールド。一番奥のピンクがジニア、だな」 「……さすが…。やっぱり詳しいのね…!」 すらすらと名前を言えるジョーに、アルテミスは心底感心した。 「こんなの詳しいうちに入んねえよ。ガキ共だって知ってるさ」 手渡されたマフィンをぱっくりと半分にしたジョーは、アルテミスの背後に立っていたパメラの前にしゃがみ、 「おまえもちゃんと覚えるんだぞ、お花のお名前」 と言いながら、マフィンを手渡した。 「ここの家族なんだからな」 のそりとマフィンを受け取ったパメラは何も言わなかったが、静かに目線を上げてジョーを見た。パメラが初めて顔を上げたので、アルテミスは内心驚いたが黙って見守った。 「いいか、オレはナクアより兄ちゃんだから、ここじゃ一番偉いんだぞ。オレの言う事はちゃんと聞けよ。 おまえは一番チビの妹だ。でも、まだおまえよりチビのタカトがいたな。おまえはタカトの姉ちゃんだ。な!」 パメラは無言でジョーをじっと見ていた。ジョーも、パメラの瞳を覗きこんでいたが、やがてパメラの頭をくしゃくしゃして「食え」と笑った。立ち上がったジョーにアルテミスはコーヒーを差し出した。それを啜ったジョーは、万人向けの微糖味なので苦いと文句を言いながら、甘いマフィンを口に放り込んで味を調節していた。 ふとすぐそこに、紫色のビクトリアブルーがぽつりと咲いてるのをジョーは見つけた。種が零れて、ここで芽吹いたのだろう。ジョーは小さめの花を摘むと、パメラのワンピースのポケットに挿した。 「家族の印だ」 「印?」 思わず訊ねたのはパメラではなくアルテミスだった。 「こいつの花言葉は家族愛ってな」 本当は、この紫色のサルビアには固有の花言葉があったが、サルビア全体の花言葉として「家族愛」があったので、ジョーはその言葉をパメラに贈った。そうしてパメラに向かって、親指を立てて握った拳を力強く出した。パメラは口をぎゅっと一直線に結んで、その拳を見つめていた。そんな二人を見て、実はしっかりとコミュニケーションが取れつつあるのではないかと、アルテミスは思った。 畑から帰ると、台車などは子供に任せて、アルテミスはすぐに洗濯物を取り込みにかかった。秋の夕暮れは案外せっかちなので気が急いた。竿を下ろしてはシャツを手繰り寄せ籠に落として行く作業を繰り返しながら、この裏庭にもコスモスに紛れてビクトリアブルーやスプレンデスがあちこちに零れ咲いているのに気が付いた。花言葉は家族愛。茎にたくさんの小花が行儀良く付いている形状が、家族なのだろうか。だとしたら大家族だ。まるでここのように。 この花をパメラのポケットにジョーが挿していた事を思い出した。ジョーは、溶け込めないでいる幼いパメラが気になって仕方がないのだろう。 朝、聞いた話を思い返す。身動きの取れなくなるほど変形した車内で奇跡的に無傷だったパメラは、だからこそはっきりした意識で、生きている両親の命が消えて行くのを見ていなければならなかったのだ。ほんの四歳。 深く溜息をついて、最後のシャツを籠に入れ終わり顔を上げると、パメラが立っていた。アルテミスと目が合った瞬間、ふっと彼女は俯いた。でも、確かに目線は合った。見ていたのだ。アルテミスは思い切って声をかけた。 「パメラ、これ持ってくれる?」 するとパメラは顔を上げた。アルテミスは逸る気持ちを抑えながら、 「お願い、私、手が一杯なの」 とダメ押しをしてみた。パメラはおずおずと歩み寄って来て、洗濯バサミの入った籠をアルテミスから受け取った。 「ありがとう」 アルテミスは洗濯物の入った大きな籠を持つと歩き出した。パメラも黙って付いて来る。これはどうしたことだろう、どんな心境の変化なのだろう。 ふと、朝のジョーの言葉が浮かんだ。 “ロボじゃない、生身の根性みせてやれ”―――生身の根性とは……いったいどんな根性なの? 知らずうちに溜息を付いたアルテミスのスカートに何かが当たった。見下ろすと、パメラの手がにゅっと伸びていた。手の主も、こちらを見上げている。きゅっと口を結んでアルテミスを見上げながら、ぴんと手を差し出しているのだ。アルテミスはそっとその手を握ってみた。パメラもはっきりと握り返して来た。そして、正面に向き直ると歩き始める。 そうして二人は夕焼けに染まり始めた庭を後にした。 その夜。夕食の終わった食堂で、当番の子供たちと後片付けを終えたアルテミスは、入浴の順番をここで待っている子供たちの中にパメラを見つけた。パメラは窓にへばりついて、ガラス窓に室内が映り込むのを遮ろうと両の手で囲いながら、必至に外を見上げている。 「お星様、見たいの?」 アルテミスは声をかけた。振り向いたパメラは小さく頷いた。初めてはっきりと会話が成り立ち、アルテミスは密かに感動した。パメラにしてみれば、それほど星が見たいというわけだ。 「見に行こうか」 言いながら差し出してみた手を、パメラは握って立ち上がった。 「ちょっとだよ」 自分の手をしっかりと握る小さな手の柔らかさ。アルテミスは頬が緩むのを堪えられなかった。 真っ暗な裏庭は屋敷の灯りを背にしてしまえば、星空を隠す事無く見せてくれた。降る様な星空、である。大地で見る本物の星空は、地平線との境がとりわけ美しいとアルテミスは思っていた。 パメラはきょろきょろと星空を見上げている。 「星座、探してるの?」 訊ねてから失笑した。四歳に星座だなんて。案の定、パメラから返事は無い。 「……。お星様、きれいだね。お空に一杯だね。楽しそうに光ってるね」 “生身の根性”が思い浮かんだ。こんな時、パメラに気の利いた一言を……と思いながらも、何も出てこない。その気持ちがそのまま言葉になって出てしまった。 「お星様の歌、知ってたら歌えたのになぁ。ごめんね。私、何も覚えてないの。全部忘れちゃったんだ。お歌もそうだしパパやママの事も全部。顔も覚えてないの」 パメラと繋いでいた手がぐいと引っ張られた。何事かと思いながら、引かれるままにしゃがみ込んだアルテミスの頭を、パメラがそっと撫で始めた。口を真一文字に結んで真剣な表情は、一生懸命という姿だ。 (これは……もしかして私、慰められてるの?) アルテミスは目を閉じて、頭にある手の感触をしみじみ味わった。なんて気持ち良いんだろう。小さな手はとても温かく感じられ、何かを許されたような、泣きたいような、充分に満たされたような安心感や幸福感が胸いっぱいに広がった。 「ありがとう、パメラ……」 パメラはしばらく、撫で続けてくれた。 翌日の昼食時。 「あ、降ってるよ!」 窓の外を見た子供が叫んだ。まだ真昼だというのに薄暗い大地へ、低い空いっぱいに広がった黒い雨雲から、雨が零れ始めていた。 「予想より早かったな」 溜息まじりにぼやいたジョーの隣でナクアが訊いた。 「今日はもう上がりかな?」 離れた席にいたセヴァが大声で言った。 「皆聞けー。ここまでの作業は前倒しで来てるから、今日の午後、休みにしても大丈夫だ。だから、お昼を食べたら自由にする!昼寝してもいいし、勉強してもいいし、ジョーと遊んでもいいぞ!」 突然振られてジョーは咽たが、そんなコトはお構い無しに子供たちは歓声をあげて、残りの食事をかき込み始めた。 そんな中、アルテミスの側に座っていた女の子達が残念そうな声で 「流星群、大丈夫かな」 「う〜ん……」 と話しながら、窓の外をチラチラと見やった。 「流星群?」 アルテミスは訊ねた。 「明日なんだけどね、来るんだよ」 「大流星群。すごいんだよ、一時間に百個ぐらい落ちるって」 「降るみたいに見えるって」 それは綺麗だろう。アルテミスは隣にいるパメラに言った。 「明日の夜、流れ星がいっぱい見られるんだって。お空の星が全部落っこちるって。楽しみだね」 しかしパメラはアルテミスを振り向くことはなかった。星の好きなパメラには楽しめるイベントになるのではないかと思ったアルテミスは、無反応なパメラにちょっとがっかりしたが、急に何もかも打ち解けるわけではないと思い直した。 秋雨は日が暮れるまでしとしとと降り続いた。昼食後は自由だとセヴァは言ったが、ジョーには自由がなかった。ずっと子供たちと格闘技ごっこをし、疲れたらそのまま子供たちとごろ寝をし、おやつを食べて子供向けの映画を一緒に観た。アルテミスは外に干せなかった洗濯物を乾燥部屋に入れたり出したりしながらも、子供たちに強請られ絵本を読まされたりした。時折、パメラを確認したが、雨に煙る景色をじっと眺めている姿ばかりだった。 その夜の事だった。アルテミスは廊下でパンジーの女の子達に声をかけられた。パメラがいなくなったという。 「おねえさんのところに行ったのかと思ったんだけど……」 「探してみよう。他の子達にも言って手伝ってもらって」 アルテミスは、彼女達に屋敷内をもう一度良く探すよう言って、自分は外へ出た。 幸いにも雨は上がり、雨雲が走っているかのような速度で夜空を流れているので、月が見え隠れしていた。星も雲間からちかちかと潤んでいる。 アルテミスはパメラの名を叫びながらずんずんと丘を上り下った。 「おねえさん!」 背後から呼び止められた。ナクアが追いかけて来ていた。 「そっちは行かないで、川があるんだ。雨で増水してるから危ないよ」 ナクアの言葉に、アルテミスの直感がびりりと震えた。 増水。嫌な予感がする。耳を澄ますと、ごうごうと流れる水の音が聞き取れた。アルテミスは走り出した。ナクアが呼んでいるが、呼ばれるほどに胸に暗い予感が広がった。予感を吹き飛ばすようにパメラの名を叫び、予感から逃げるように走った。 ―――どうしよう、見てろってジョーに言われたのに……! 「止まって!おねえさん!」 さすがに従って止まったアルテミスのすぐ先は崖だった。崖下に川があるようで、激しく流れる水音が昇って来る。ちょうど雲が途切れて月明かりに照らされた崖下を、アルテミスは覗き込んだ。真っ黒い大蛇のような濁流がのた打ち回っているのが見えた。そして、アルテミスの祈りも虚しく、壁にへばりついている小さな白い影が目に飛び込んで来た。 「パメラ!」 悲鳴にも似たアルテミスの一言で、ナクアも覗き込んだ。 「あのバカチビ…!」 「ナクア、ジョーに知らせて!」 アルテミスはそう言うが早いか、緩やかな斜面を見極めて崖を下り始めた。 「おねえさん!無茶だよ!」 ナクアは焦った。だが、アルテミスは引き返すはずも無く、 「早くジョーに!」 と今一度促し、ナクアの手の届かぬところへ下りてしまったので、ナクアに出来ることと言ったら、アルテミスの伝言を逸早く届けることだけだった。彼は屋敷へ向かった。 雨でぬるぬるとぬかるんだ壁を足場を探しながらアルテミスは下りた。小さなパメラがこの崖を下りられたはずは無い。誤って転落したに違いない。そしてその時はまだ、川幅が今ほどはなく、柔らかい草の生い茂った川岸があったのだろう。その草が彼女を優しく受け止め、川に転がり落ちるのも防いでくれたに違いない。しかし今は、すでにその川岸は無く、川幅は崖の斜面いっぱいだ。短時間で大幅に増水したということだ。川上で堰が決壊したのか、それは確かめようが無いが、とにかく、今がピークでこれからは減るのなら良いが、ますます増えるのかもしれない。そうなったらパメラの立っている足場も飲み込まれてしまう。一刻も早く引き上げなくては。 「パメラ!今行くからね!」 濁流の音に書き消えない位置まで下りられたアルテミスは、パメラに声をかけた。パメラは驚いて顔を上げた。月明かりの中、斜面にへばりつきこちらを見ているアルテミスを見つけ、パメラはか細い声を絞り出した。 「姉ぇね……っ」 パメラに初めて呼ばれたアルテミスは、瞬間的に体中が満たされた。認識され必要とされた喜び、幼い命を絡め取ろうとしている死神への怒り、失いたくないと切望する気持ち。ぐるぐると胸の中で渦巻くそれらを原動力にして、アルテミスはパメラへと辿り着いた。 手を伸ばしてパメラをしっかりと抱き寄せた。パメラもしがみ付いてくる。 「大丈夫、もう大丈夫よ。良かったパメラ、無事で良かった」 彼女の小さな体は冷え切っていた。その泥だらけの背中や肩をさすりながら、 「心配しないで、すぐにジョーが来て、引っ張り上げてくれるからね」 と言った。パメラはずっと泣いていたようで、しゃくり上げている。 「大丈夫、大丈夫。もう怖くないから。大丈夫」 その時、ぽろりと足元の土が崩れて、濁流へと落下して行った。大人の体重には耐えられなかったのか。アルテミスは片足分しかない足場に立ち、パメラを抱き締め、何度も頭の中で繰り返した。 (パメラは死なせない!そして私も一緒に助かる!パメラの目の前でもう誰も死んじゃだめ…!だめなの…!) パメラの心が永遠に閉じてしまう事は避けたい。だから…! しかし、パメラを抱いている腕は痺れ、全てを支えている片足も膝から折れそうになって来た。 いよいよ苦しくなったアルテミスは、パメラの髪に顔を埋めて呟いた。 「ジョー……!」 その瞬間、ガッと肩を掴まれた。驚いて顔を上げると、雲間から出た青白い月を背負ってジョーがいた。アルテミスを挟むように斜面に両足を付けて宙に浮いている。 「ジョー…!」 「パメラを」 ジョーは、パメラをアルテミスの腕の中から抱き取ると、 「よし、いい子だ。これから上に上がるからな、おとなしくしてろよ?」 と言い、右手でしっかりとパメラを抱えた。 「お願い、どうか無事に、」 「おう」 ジョーのこの短い返事は、とてつもなく安心感があった。もう大丈夫。ジョーに任せておけば何も心配は無い。 「OK、あがる」 インカムで崖上と繋がっているのだろう、ジョーの身体に固定された綱が上昇し始めた。 ジョーの腕の中でパメラが叫んだ。 「姉ぇね…!」 見上げているアルテミスに向かって、小さな手を伸ばす。アルテミスは、パメラを勇気付けようと、笑って「大丈夫よ」と言おうとしたが、 「大丈夫だ。絶対アイツも助ける」 と、ジョーが先に断言した。そしてあっという間に崖の上へ消えて行った。 見上げていたアルテミスの足場がさらに半分に崩れた。パメラを抱いていたので壁を背にしていたアルテミスは、かかとしか乗れていない状態になり、今更体の向きを変えることなど出来るはずも無く、身じろぎもせずに耐えていた。が、その僅かな突起さえとうとう壁面からぼろりとこそげ落ちた。 あっと思った瞬間、水面に打ち付けられる衝撃ではなく、抱き寄せられる浮遊感に全身が包まれた。 わけが分からず、目を開くと、ジョーの顔があった。もうどこにも立っていないアルテミスは、ジョーの腕に抱えられているだけだった。 「……ジョー…」 「ギリセーフ」 「パメラは?」 「無事。上でセヴァがみてる」 良かったと心底思った。 「ごめんなさい、こんな事になって…。ちゃんと見てろって言われてたのに」 「あ? おまえはパメラを助けたじゃねーか。つか、おまえ、オレにばっか抱えさせてねーでつかまれよ。オレ様の腕が折れちまうだろうが」 ジョーのその言葉は優しさだと、アルテミスにはもう良く分かる。月明かりの中、アルテミスはジョーの首に腕を回して、しっかりと抱きついた。ジョーの煙草の香りが安心感を煽る。ジョーがいる。何も心配ない。 「ありがと、ジョー…」 パメラのコトも、自分のコトも。心からアルテミスは感謝した。涙が滲む。 しがみ付いたまま、どうやら啜り泣いてるアルテミスを抱きながら、ジョーは自分の中にぐずぐずと湧き出す気持ちに戸惑っていた。 戸惑いながらも、彼女の細い身体をしっかりと抱え、その存在を腕の中に味わっていると、やたらと満ち足りた気分で胸がいっぱいになるのだった。 「ジョー!」 ふいに、ジョーの耳元からナクアの声がして、二人は我に返った。 「聞こえてる? 大丈夫? 何か急にそっちの声、はっきり聞き取れなくなったんだけど! 痛て!」 ナクアの必死の呼びかけは、痛いという悲鳴で終わった。 ジョーは、アルテミスを抱え直し、 「行くぞ」 と言うと、引き上げるようインカムで崖上へ指示した。 そうして、斜面に一つの影を落としながら、二人は上昇して行った。 崖上の草むらに立った時、パメラが泣きながらアルテミスにしがみ付いてきた。二人とも泥だらけだったが、アルテミスはパメラをぎゅうぎゅうと抱き締め、頭やら顔やらにキスした。 ロープを器用にまとめながら、目の端でそんな二人を眺めていたジョーは、 「ご苦労さん。いやぁ、泥が付いてても男前だな」 と、セヴァに左頬を指された。 「あれ、お揃いか?」 セヴァはジョーの耳元で囁きながらアルテミスをちらりと見た。確かに彼女の左頬も泥が付いている。セヴァは左頬同士が触れた事を知っていて、冷やかしているのだ。ところがジョーは軽口で言い返す事ができず、黙ってロープを一つの輪に束ね上げた。 ジョーのロープを牽引していた機械を地面から引き抜いているナクアは、 「何で蹴るんだよ、ひどいよ、セヴァ」 とブツブツ言いながら尻をさすっている。 「人の何タラを邪魔する者は、馬に蹴られて死んじまえって言うんだよ」 愉快そうに言いながら、セヴァはパメラを抱き上げた。 「何タラ? 何だよそれ。魚?」 高笑いしながらパメラを抱いて歩きだしたセヴァの後を、ナクアは納得できずに機械をガコガコ引き摺りながら追いかけた。 何タラの部分を知っているジョーは、セヴァをどつきたい衝動に駆られたが、ふと横に立つ、ナクア同様意味の分かっていないアルテミスの、泥と涙でぐちゃぐちゃな笑顔を見たら………。そう、弱々しくて泣き笑いみたいだけれど、彼女は笑顔だった。 ジョーは、セヴァの冷やかし等もうどうでもいい気分になった。右肩にロープを担ぐと、左手でアルテミスの手を取り、しっかり握って歩き出した。 翌日は、昨日の雨が嘘のように快晴だった。 洗濯物を干し終わったアルテミスは、パンジーの部屋のドアを開けた。パメラは冷え切ったせいか軽く発熱してしまい、今日はベッドの中で休んでいるようセヴァに言われていた。息遣いが静かになっている。そっと計測してみると、熱は平熱に下がっていた。良かったと安堵の溜息を漏らすと、パメラが目を覚ました。 「もうお熱は下がったよ。おとなしく寝ていれば、夜の流星群、見ても良いって。良かったね」 アルテミスは微笑みながら言った。が、パメラの表情はみるみる曇り、今にも泣きそうな顔になって鼻がひくひくしている。 「パメラ…? ねえ、流れ星は、キライなの…? お空に何を探してたの?」 アルテミスはそっと訊ねた。 「………お星さま…。ママと…パパと…姉ぇねの……」 「え……」 「…ママ達は、お星さまになって、パメラをいつもいつも見てるよって……ママ言ったの」 アルテミスは息を呑んだ。潰れた車内で、触れることの出来ない位置から、一人取り残されるであろう幼い娘に、母親が命の限りを込めて贈った言葉か。 寂しくなったら空を見上げて。ママもパパもお姉ちゃんも、みんなパメラの事を見てるからね。一人じゃないよ。 「今日、お空の星が全部落っこっちゃったら、お空にママ達いなくなっちゃう。ねえ、どこに落ちるの? 拾いに行く………」 しゃくり上げているパメラの手を握って、アルテミスは言った。 「違う、違うんだよパメラ。お空の星はなくならないの。流れる星はね、お空のもっと向こうの遠いところから飛んで来る星のかけらなの。だからね、ママ達の星とは違うんだよ。ママ達はずっと同じところにいるんだよ」 「………ほんと……?」 「本当!」 なかなか不安の取れないパメラは何度も本当かと訊いた。そしてアルテミスは全てに誠意を込めて本当だと答えた。 そうしてようやく涙が溢れる瞳が弓状に反って、パメラは笑顔になった。 「……よかったぁ〜……」 「ごめんね……! 私が変な言い方しちゃったから……ごめんねパメラ、ごめんね」 パメラの涙が止まると、アルテミスの番だった。自分が情けなくて泣けて来る。本当に可哀想な事をしてしまった。昨日から、どんなにこの小さな胸を痛めていたのか。 パメラの手を握ったまま嗚咽していると、パメラはその手を抜いてアルテミスの頭を撫で始めた。もういいんだよ。そんなに泣かないで。とでも言うように。 「……パメラ……」 小さな彼女の大きな温かさが沁みて、ますますアルテミスは涙が溢れた。 「ほんとに泣き虫なんだね」 頭を撫でながらパメラは言った。 「……え?」 「なんでもない」 急に真面目な顔になって黙ったパメラの胸の奥には、自称ここで一番偉い長兄からの言葉があったのだ。 “あのお姉ちゃんは、大人のくせにすごい泣き虫なんだ。だから、おまえ、見張っててくれよ。それで、悲しそうにしてたら、慰めてやってくれな。頼んだぞ、パメラ” パメラはあの夜から、ずっとそれを実行して来ていたのだった。 その日の夜。セヴァ・ファームの住人達は、セヴァとマークが庭に用意してくれたシートに並び、毛布に包まりながら雲ひとつ無い晴天の星空を見上げていた。 きらきらと瞬く星々の間を、長い尾を引いてぱぁっと輝きながら流れ星が落ちて行く。漠然と見ているだけでも、すぐに見る事が出来るほどの頻繁さで夜空を横切った。 そのたびに子供たちから歓声が上がった。 女の子達と夜空を見上げているアルテミスは、星が流れるたびに心の中で早口に願った。 この子達が幸せでありますように。いつも笑っていられますように。この先の人生は、悲しいことがちょっとでありますように。 アルテミスの隣ではパメラが瞳をキラキラさせながら流星を数えていた。10まで数えると1に戻ってしまう幼さが愛おしい。アルテミスはパメラに、 「今夜はずいぶん賑やかだわって、ママ達も驚いてるかもね」 と囁いた。するとパメラは言った。 「うん。でもきっと、ここみたいに楽しいって言ってるよ」 確かに騒々しい。夜の庭なのに。しかし、お隣さんもはるか彼方なのだから聞こえやしない。たとえここで毎晩ダンスパーティーをしても何の問題もない程の、広大な大地なのだ。 「そうだね、楽しいね!」 アルテミスは晴れやかな気分で、パメラと笑い合った。 「ジョー。おねえさん、笑ってるね」 ナクアが嬉しそうに言った。ジョーももちろん確認済みだ。 「でっけえ口だよな」 「でも可愛いじゃん。俺、好みだな、告ってみよっかな」 言い終わらないうちに、ナクアはぽかっと殴られた。 「ませた事言ってんじゃねーっての」 「なんだよ、彼女じゃないんだろー、いいじゃんかよー」 グランレースの打ち上げの夜、ビーチハウスのキッチンで花を髪に挿した時に見たきりだったアルテミスの笑顔。ようやくそれが彼女の顔に戻ったのだ。ようやく。 ジョーは満足してシートに寝転び、星空を見上げた。流れる星だろうと、瞬く星だろうと構わずに、あの笑顔が二度と消えないようにと願った。 |
||
| 第20話 星に願いを END |
<<TOP <<BACK NEXT>>
 ぺた ぺた |
 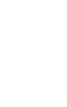    |